
「発明」はいろいろな未来を可能にする。「誰一人取り残さない」というSDGsの基本理念を実現した発明がある。体に障がいがあっても演奏を楽しめる「だれでもピアノ」だ。JSTの令和3年度「STI for SDGs」アワードで文部科学大臣賞に輝いた「だれでもピアノ」は、一人の障がいをもつ高校生の願いを実現するために開発された。チームを率いたのは東京藝術大学特任教授の新井鴎子さん。技術面ではヤマハが支えた。
メロディーに合わせて伴奏
「どの曲にしますか」。グランドピアノのいすに座った演奏者に、新井さんが曲のリストを見せながら尋ねる。「きらきら星」「ふるさと」「エリーゼのために」……。選んだ曲を演奏者が弾き始める。ただ、演奏者が弾くのはメロディーのみだ。ある人は楽譜を見ながら指1本で一音ずつ、ある人は5本の指を使って滑らかに、ある人は新井さんに次の音を指さしてもらいながらゆっくりとメロディーを弾く。
すると、あたかも演奏者自身が弾いているかのように、メロディーに合わせてグランドピアノが伴奏を奏でる。速く弾けば伴奏も速くなる。つっかえてメロディーが止まると伴奏も止まり、再び弾き始めるとそこから伴奏も始まる。伴奏にはペダルも付き、プロのピアニストが弾いているような華やかなものだ。弾き終えると聴いていた人たちから温かな拍手が送られた。
2021年秋に和歌山県で開催された、第36回国民文化祭「紀の国わかやま文化祭2021」での「だれでもピアノ」の体験コーナーでの一コマだ。「だれでもピアノ」はその名の通り、子供から高齢者まで、誰もが演奏を楽しめる。「楽しかった」「感動した」「もう一度弾きたい」「何度でも練習したくなる」――体験した人は口々に演奏の喜びを話した。

本物の楽器を弾きたい
「だれでもピアノ」は、文部科学省とJSTによる産官学連携プロジェクトである「東京藝術大学COI(センター・オブ・イノベーション)拠点」において開発された。研究開発グループの一つとして「インクルーシブアーツ研究」が設けられ、チームは体にハンディキャップがあっても演奏を楽しめる楽器の開発に着手した。
当初は既存の楽器を演奏しやすいように改変するか、簡単に演奏できる楽器を新たに考案する方向での開発を考えた。しかしその考えは、重度の肢体不自由の生徒が通う特別支援学校の高等部を訪問した時に覆されたそうだ。そこでは身体に障がいのある生徒らが、好きな楽器で好きな曲を弾こうと思い思いに取り組んでいた。ショパンの「ノクターン第2番」を弾きたいという生徒は、脳性まひがあって車いすでの生活を送り、右手の指の一部しか自由に動かせない。それでもグランドピアノの鍵盤に顔を近づけて、顔を真っ赤にしながら、1本の指で一音一音、ノクターンのメロディーを弾いていた。横から音楽の先生が手足を伸ばして伴奏をつけ、ペダルを踏む。生徒の顔にはほほ笑みが浮かび、ピアノを弾く喜びが全身から伝わってくる。
新井さんは衝撃を受けると同時に、「生徒らはプロの演奏家と同じ本物の楽器を弾きたいという願いを強く持っていて、障がい者用に特別につくられた楽器を弾きたいのではないんだということを思い知った」という。

東京藝大のコンサートに出演
新井さんは障がいのある生徒にピアノの演奏を楽しんでもらうことに決め、生徒のメロディーに自動で伴奏をつける技術が開発できないかと、自動演奏ピアノの最先端の技術をもつヤマハを訪ねた。
実現には、あらかじめ伴奏データを作成する必要がある。しかし、どのようなテンポで演奏され、どこで止まるかわからないメロディーに、不自然にならないように合わせる伴奏データの作成は難しく、特にペダルの調整には苦労したそうだ。優れたピアニストのペダルを踏んだり上げたりする速度や角度は何千通りにもなるという。どこで止まってもペダルが最適の状態になっていなければ、「美しい響きをつくることができない」(新井さん)。生徒の演奏の特徴を分析し、現場での課題を特別支援学校と新井さんら東京藝大チーム、ヤマハの三者でコミュニケーションを取りながら解決し、「だれでもピアノ」が開発された。
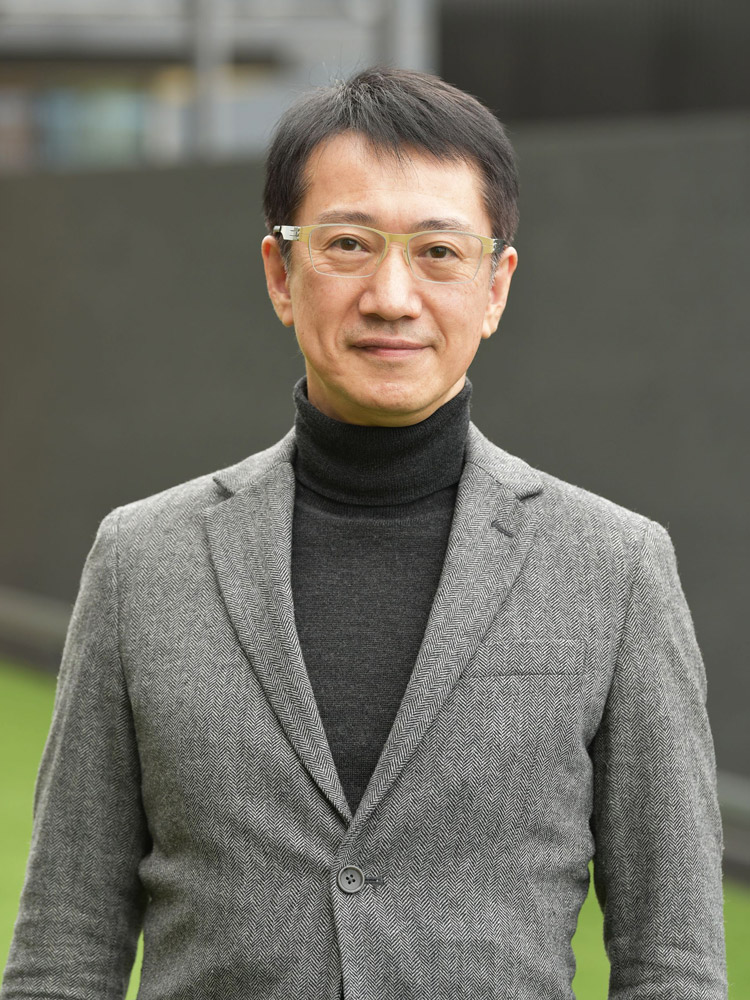
当時、ヤマハの研究開発部門の部長を務めていた田邑元一さんは、生徒のモチベーションは、楽器が演奏できればいいということではないと感じたという。「自己のアイデンティティー、一人の人間としてこういうことができるんだということを自分で確かめ、人にも見せたいというところに根源があるのだと感じました」
生徒らは東京藝大の「藝大アーツ・スペシャル~障がいとアーツ」のコンサートに出演し、思い思いの曲を奏で、大きな拍手を浴びた。「だれでもピアノ」の開発に着手してから、わずか5カ月弱だった。
障がいは芸術の新しいアイデアの源
新井さんは、障がい者を何かができない人ではなく別の能力をもった人、障がいを芸術の新しいアイデアの源ととらえて「障がいから学ぶ」ということをモットーに、2012年から東京藝大で「インクルーシブアーツ」に取り組んでいる。インクルーシブとは、包含している様子の意味で、あらゆる人が排除されないことを意味する。

「誰もが楽しめる『だれでもピアノ』ですが、元はたった一人の障がいをもつ高校生の、『ショパンのノクターン第2番を弾きたい』という願いをかなえるために開発されました。目の前の『その一人』を救えないものは誰も救えない。身近な人の、身近な問題を解決していくところから、大きなインクルーシブが始まるのだと考えています」(新井さん)。
田邑さんは、「だれでもピアノ」が汎用(はんよう)性をもった背景には、新井さんの、既成の概念にとらわれない発想があったと考えている。「『だれでもピアノ』は一見、障がい者のニーズを満たすために開発されたように見えますが、新井先生がそこに新しい創造性を見いだし、『これでしょう』とゼロをイチにするような思考で課題を明確にしたからこそ、新たな価値をつくりだす成果を生みだせたと思います」
高齢者にも遠隔地にも広がる可能性
現在は、インターネットを使ったリモート演奏のシステムが開発されており、例えば自宅のキーボードから、遠隔地にある「だれでもピアノ」を弾くこともできる。音の遅延は、ヤマハの技術で解消した。
人工呼吸器をつけていて寝たきりのある小学生は、このシステムで自宅からキーボードを通して、公共スペースに設置されたフル・コンサートグランドピアノ版「だれでもピアノ」を演奏した。その後どうしても自分が演奏した「だれでもピアノ」が見たくなり、ストレッチャーに乗って見に行ったそうだ。ピアノに触れ、「こんな手触りなんだ」と感触を確かめていたという。
また、「だれでもピアノ」専用のアプリの開発も進められている。
2017年から全国で「だれでもピアノ」のワークショップを行い、のべ1500人が同ピアノを体験し、伴奏データの種類も増えた。
「片手でメロディーを練習すれば、ピアニストのような伴奏がついて完成度の高い演奏ができるようになる。それを他人に見てもらうことによって大きな達成感を得て、自己効力感が高まったり、承認欲求が満たされたりするという新たな気付きがありました」と新井さんは話す。認知症の進んだ高齢者が、ピアノを弾いて拍手を受けて大きな喜びを感じている姿を改めて確認でき、高齢者の生きがいの創出という面からも研究が進められている。
「生きがいや希望をもって生きるのが一番、人間らしい生き方だと思うし、動物と人間の大きな違いって、感動する能力だと思うんですね。その感動する能力を使って生きることが、よりよく生きることなんだと思います。音楽や美術、アートというものは、そこに大きく関わる要素だと感じています」と新井さんは話してくれた。
また、新井さんは「だれでもピアノ」を開発する中で、科学技術も芸術と同じではないかと感じたという。「芸術と同じように、科学技術の発展を後押しするにも心の動きが必要ではないでしょうか。これがやりたい、あそこに行きたい、というような人の心の動き、感動が原動力になって、科学技術の発展があるのだと思います」(新井さん)。
想像力を磨くことがインクルーシブな社会につながる
新井さんは今後、社会的な孤立を防ぐ面でも「だれでもピアノ」が大きな役割を果たすと考えている。
「ピアノというのは場所に属する楽器なので、ピアノのあるところに人が来て人の輪ができ、コミュニケーションが生まれます。「だれでもピアノ」が公共の空間で、公共的な役割を果たしてくれればと期待しています」
将来的には、「『だれでもピアノ』を通じて人間の多様性を学び、分け隔てがなくなって、障がいとあえて言う人のいない社会になるといいと思っています。たまたま障がいのある人もない人も居合わせて、お互いに想像力を働かせ、手助けが必要な人がいれば自然と手を差し伸べることができる。そういった想像力を磨くことが、インクルーシブな社会をつくる一番の原動力になると思っています」
さまざまな可能性を秘めた「だれでもピアノ」。今後の発展に大きな期待が寄せられている。

新井鴎子(あらい・おーこ)
東京藝術大学特任教授・横浜みなとみらいホール館長
東京藝術大学楽理科・作曲科卒業。クラシックコンサートやテレビの音楽番組の構成・監修などを手がける。NHKの音楽教育番組の構成で国際エミー賞入選。「障がいとアーツ」をテーマに研究を進め、ワークショップやデバイスの開発にも関わる。


