よりよい未来社会のあり方を科学者と市民が考える科学技術振興機構(JST)主催のイベント「サイエンスアゴラ2020」。その口火を切る開幕セッションでは科学技術のあり方や社会との関係性をめぐり、識者らの熱い議論が交わされた。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大でオンライン開催となったのを受け、登壇者の一部が日本科学未来館(東京都江東区)で、一部がリモートで参加する形で実現。スピーチに続くディスカッションでは、未来に向けて進むため今、科学技術や私たちにできることをめぐり、5人が考えを深め合った。
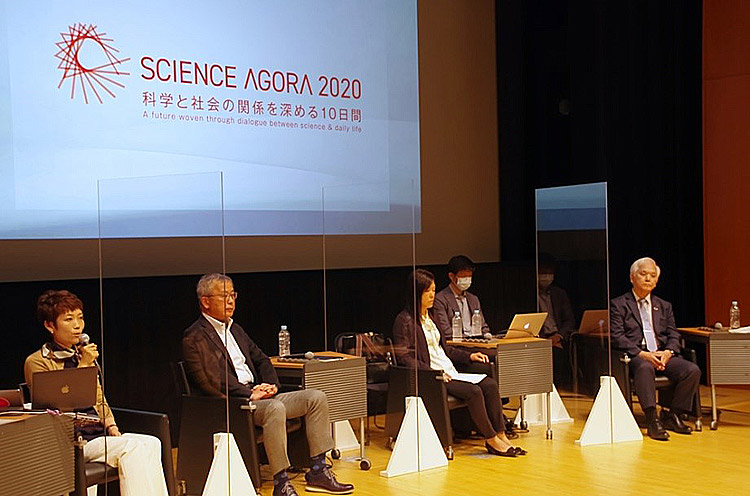
研究成果の社会実装に「大きな壁」
ディスカッションは11月15日に開かれたこのセッションの後半で実施され、2つのテーマで進んだ。最初の論点は「目指す未来社会像に向け、研究開発成果を社会や産業につなぐには」というもの。冒頭、進行役を務めたインキュビオンCEOのタカハシショウコさんが「研究成果と社会実装の間に大きな壁があり、未来に向かうには私たちがそれを超えねばならない。何が不足していて、どう取り組めばよいのか」と問題提起した。
米IBMフェローの浅川智恵子さんは「新技術をどうすれば早く社会実装できるかという壁に当たっている。社会実装するにはそれぞれの組織の承認が必要。組織にニーズがあるものは承認や導入が早いのに対し、研究者側から示すものや、まだ製品になっていないものが理解されるのは難しい。イノベーションを進めるには、組織と社会の理解をクイックに進める必要がある」と厳しい現状認識を吐露した。

この承認の壁について、JST理事長の濵口道成さんは「コロナウイルスを不活化する技術はできているが、承認の問題に悩んでいる。日本社会は高度化し、生涯同じ仕事をする人が多く社会が縦割りになるなど、ガチガチになっている。また『長期的研究』といったとき、大学は10〜20年だが、企業は3年と捉えるなど、ずれがある社会だ」と指摘した。
「科学技術の不確定要素、正直に語るべきだ」
濵口さんは今、社会に求められる概念について話を進め、「自分の人生を決めるのは自分自身。大切なのは、インフォームドコンセント(丁寧な説明と心からの同意)ではないか。専門家も完全に予測できないこともある。そのために『こういう可能性がある』と現状を説明して了解してもらうことだ。話し合い、他人の痛みが分かる、お互いに納得して次のプロセスを決めていくことが必要になる。互いに納得する文化が必要な時代になっていく」と説いた。
「壁を越えるのはそんなに難しいのか」と畳みかけて問うタカハシさんに、濵口さんは「科学には不確定要素があるのに、万能だと信じてもらわないといけないという幻想を、科学が抱いている。正直に事実を提供することが必要だ」と投げかけた。
2人の言葉を受け、タカハシさんが「クイックになるための処方箋やアイデアは」と問いかけると、経営共創基盤IGPIグループ会長の冨山和彦さんが「企業などで物事を60%で決められることは、結構ある」と切り出した。
冨山さんは続けて「ところが、意思決定に関わる人が増えるほど『それは、いかがなものか』という人がいて、そこで止まってしまう。トップ同士で話し合っても、その話が部長や課長に行って行方不明になる。リスクを取れるトップがパッと決めないと問題をクリアできないのに」と、自身の経験に基づいて指摘した。また日本企業の人材の非流動性を問題視。「東大や京大を出たエリートが同じ会社で30年も40年も働く社会は、どうかしている。毎年10%くらいは流動する社会にならないと」と話した。

NTT会長で総合科学技術・イノベーション会議議員の篠原弘道さんは「科学技術では、アカデミアと経済界の連携、流動性を高めねばならない。基礎研究は世界一よいものを作ろうと動くが、社会実装では使い勝手が求められる。社会実装を増やし、互いを活性化するためには流動性が必要だ」と強調した。
「文系と理系の枠、取り払う発想を」
続いての論点は「私たち市民は、科学技術とどのような視点で向き合い、誰とどのような対話を重ねていけば、科学技術と手を携えてより良いLifeを作っていけるのか」。タカハシさんは「どうすれば科学技術が市民の判断の拠りどころになり、生活をよりよくしていこうという力の源になるか。どんな対話が必要なのか」と問いかけた。
京都大学こころの未来研究センター教授の広井良典さんは、コロナ禍の現状に触れて話を進めた。「欧米とアジアで拡大状況が違うことの理由など、分かっていないことが多く、しかも専門家でも見解が違う。真理が科学によって解明されて市民が受け取る、という発想から脱却することが出発点だ。ただ懐疑論になるのではなく、未知のことを一緒に明らかにしていく発想と、科学者と市民が同じ立場にあるという視点で考えていくことが重要だ」
広井さんはその上で「文系、理系の枠を取り払う発想がこれからは本当に重要。科学技術基本法が改正され、人文科学も入り包括的に科学技術を考える方向になったのは大きな前進だ」とした。関連して2点を指摘した。「一つは、企業は中長期的なビジョンが見えてこない状況になっていること。大学では皮肉にも目先のことに追われ、むしろ企業の方が長い視点で考えているように思えることがある。(両者の)時間軸が接近しているようだ。二つ目は、企業が何をしたらよいか、見えなくなっていることだが、私のような文系からは地方都市の空洞化、人口減、格差など、社会課題がたくさんあることを示せる」。こうした見方を基に「大学と企業、科学と市民の距離が近づく新しい局面に入っており、この点を発展させることが重要」と説いた。

女子高生が変えたポケベルから学ぶこと
ここでタカハシさんは「世の中の困りごとを知っているのは社会の側かもしれない。ただ、市民は科学技術を知らないものだとして身構えてしまう。どういう態度で対話したらよいのだろう」と投げかけた。
これに対し篠原さんは「科学技術者が不確実性を真剣に吐露すれば、市民が受け入れると思うが、それで責められる怖さがあり、無謬(むびゅう)性を前面に押し出しかねない。社会をどうしたいかは、市民と話すことが不可欠だ。その際に大事なことは、それを使うとどうなるかという、技術の成果の分岐を探す議論をすることだ」と提言した。
篠原さんは「しゃべっていて思い出した」と続けた。「ポケベルはもともと、サラリーマンが会社から呼ばれる道具だった。それを女子高生が連絡手段として使い始め、ポケベルの意味が全く変わった。つまり、提供側が全く想定しない使い方を利用者側がすることによって、新しいことが開けるできごとだった。そこで、技術を使って何ができるか、一緒に探す方向もあると思う」などと強調した。
タカハシさんが「逆に科学技術に携わる立場から、社会に対してこうあってほしいということは」との問いに対し、浅川さんは「すごく、難しい質問。話を伺ってきて、まずは科学技術者の方から動いていかないといけないと思った。私たちは夢を持って研究開発をしているが、市民と共通言語を持って対話する機会が必要だ。その中で、(市民に)一つのニュースソースではなく、さまざまな視点で情報にアクセスして頂ければ、対話の幅が広がり深みが出る気がする」とした。
濵口さんは「コロナ禍を通じ日本には、すごくしなやかな部分があると感じた。一つは教育レベルが高いこと。IT化が進み、60代や70代の人も情報に簡単にアクセスできる社会になっている。また、『あれ、こんなことができる』と個々人が発見していること。それらを人の生きがいにつなげるプラットフォーム、ギリシャ語でいうとアゴラが必要だ。工夫しだいで、日本はすごい力を持った国であることを実感できると思う。JSTの役割は大きい」と語った。

「トーナメント戦よりリーグ戦」の人生を
参加者からは「現状維持のバイアスを解消するには、どうすればよいか」との質問が寄せられた。これには篠原さんが「失敗するかもしれないし、楽しいことがあるかもしれない。大きな失敗にならなければ、個人でも大学でも企業でも、まずやってみようという気持ちが大事。先生や親がブレーキをかけず、チャレンジを奨励する社会を作ることが大事だ」と回答した。
また冨山さんは「人生を一回こっきりのトーナメント戦みたいにやると現状維持になる。リーグ戦のように勝ったり負けたり、つまり成功も失敗もあるとよい。会社も社会も、入れ替わりを前提にしないと現状維持になる。新陳代謝を前提とした仕組みをどうするか。経営者、市民、大学、国も真剣に対峙することだ」と語った。
タカハシさんは「サイエンスに関わる方だけでなく学生、社会科学、人文科学の方にも議論に入っていただきたい。今はサイエンスアゴラというが、将来は『ヒューマンアゴラ』として、より枠組みを広げて実現できたら」との言葉を登壇者と参加者に贈り、ディスカッションを締めくくった。
コロナ禍の出口が見いだせない閉塞した現実が続く中、人々の多くは科学技術に対し、不安、いら立ちと、それでも対応策を求めるという、実に複雑な思いを抱いているのではないか。科学技術は今、社会との対話という意味でも歴史に残る試練の時を迎えている。今回のセッションは、双方の課題と距離感を整理し、再認識するひとときとなった。どちらにも変革が求められており、対話をさらに深めていく努力が欠かせない。
関連リンク


