気象庁は1日、今夏(6~8月)の日本の平均気温が平年を2.36度上回り、1898年の統計開始以来「最も暑い夏」になったと発表した。2023、24年は平年プラス1.76度でそれまでの夏の最高値だったが、この数値を0.6度更新。3年連続で最も暑い夏となり、気温上昇に歯止めがかからない状態が続いている。
同庁は今年は11月まで気温が高い傾向が続く可能性があると予測し、引き続き熱中症対策を呼びかけている。また、地球温暖化により「気温が底上げされている」とし、長期的に来年以降も極端に暑い夏が増える可能性が高いという。9月1日は関東大震災が起きた日で大地震・津波や台風を想定して制定された「防災の日」だった。これからは温暖化の影響で激甚化が懸念される記録的な猛暑や豪雨などの自然災害への備えも重要になってきた。


全国で延べ30地点が40度以上を記録
気象庁によると、8月中に群馬県伊勢崎市で41.8度を観測して国内最高記録を更新するなど、全国の多くの地点で最高気温記録を更新した。40度以上となった地点数は延べ30に上り、過去最多になった。今夏の平均気温の平年差は、北日本でプラス3.4度、東日本でプラス2.3度、西日本でプラス1.7度だった。
全国の「アメダス(地域気象観測システム)」観測地点で最高気温35度以上の猛暑日を記録した地点数積算は、現在と比較可能な2010年以降では最も多かった2024年の8821地点を超えて、9385 地点となった。また、全国153の気象台などのうち132地点で夏の平均気温が歴代1位の高温となった。猛暑日が最も多かったのは大分県日田市の55日で、山梨県甲府市と京都府田辺市がともに53日と続いた。
また、今夏の日照時間は太平洋高気圧に覆われやすかった北・東・西日本の日本海側、太平洋側の両方でかなり多かった。夏の日照時間平年比は、東日本の日本海側で140%、太平洋側で137%となり、1946年の統計開始以降、夏として1位の「多照」となった。一方、夏の降水量は、前線や低気圧の影響を受けにくかったため、北・東日本の太平洋側と西日本の日本海側、太平洋側で少なかったという。


「ダブル高気圧」状態が記録的猛暑の大きな要因
こうした過去を上回る猛暑の原因について気象庁は次のように説明している。
日本付近では今夏を通じて偏西風が平年より北に偏って流れやすく、全国的に暖かい空気に覆われた。6月から「太平洋高気圧」が日本へ張り出し、平年は梅雨期で雨が多いが今夏は梅雨前線の活動が弱く、晴れの日が続いた。
春から盛夏期に向かう季節の進行がかなり早く、東北地方を除き5月に梅雨入り、6月中に梅雨明けとなった。梅雨入り・明けが記録的に早い地域もあった。同時に「チベット高気圧」も強まり、しかも偏西風に押し上げられて北寄りを流れたために暖かい空気が流れ込んだ。2つの高気圧が日本周辺上空で重なる「ダブル高気圧」状態だった。
9月下旬までの気温と降水量の見通しについて気象庁は、全国的に暖かい空気に覆われやすいため、高い状態が続くと予測。特にこの期間の前半の気温がかなり高くなる見込みとしている。また、北・東・西日本では、6月下旬以降高気圧に覆われ、降水量の少ない状態が続いているが、向こう1カ月の降水量も、高気圧に覆われやすい。このため東日本の太平洋側では平年並みか少なくなるとみている。
11月まで高温続く可能性
気象庁は8月19日に9~11月の全国の天候見通しを公表している。それによると、11月まで全国的に暖かい空気に覆われやすく、高温が続く可能性が高いとしている。日本列島周辺の中緯度地域の大気と海洋の特徴については、地球温暖化の影響などにより大気全体の温度が高い。海面水温は太平洋赤道域の中部で低い一方、インド洋東部からフィリピンの東方海上にかけては高くなり、積乱雲がインド洋東部からフィリピンの東方海上にかけて多く発生するという。
こうした影響により上空の偏西風は引き続き、平年より北寄りを流れやすくなる。太平洋高気圧は日本の南東を中心に強くなる見込みという。また、継続して季節の進行が遅く、全国的に暖かい空気に覆われやすくなるという。


温暖化の影響疑いなく
気象庁の分析では、日本の夏の平均気温は変動を繰り返しながらも長期的には上昇の傾向にあり、100年当たり1.38度の割合いで上昇している。温暖化の影響で海面水温が高くなっており、立花義裕・三重大学大学院生物資源学研究科教授ら気象の専門家はそろって「日本近海は際立って海面水温が高い」と指摘。インド洋など熱帯の高い海面水温が日本の気象に関係する高気圧を強めたと同時に、西日本近海の高い海面水温により水蒸気が多く供給されて8月の九州地方の豪雨につながったとしている。
立花教授は以前から北極周辺の温暖化が偏西風の蛇行や流れの位置変化をもたらして近年の北半球の、豪雨や干ばつ、記録的な猛暑の大きな要因になっていると指摘し、度々、温暖化対策の重要性を強調している。また、救急医療が専門の横堀将司・日本医科大学教授は「増加している熱中症被害は今や災害級ではなく超災害級だ」と指摘し、「自ら命を守る対策」を求めている。
国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2021年8月に「第6次評価報告書」を公表。この中で「今後温室効果ガスの排出量を低く抑えても2040年までに産業革命以前から1.5度を超える可能性がある」と指摘した。その上で「1.5度上昇」により「50年に1度の熱波」が1850~1900年と比べて8.6倍も増え、「2度上昇」では13.9倍も増えてしまうと分析している。また「10年に1度の豪雨」も「1.5度上昇」で1850~1900年比で1.5倍増えるという。
今夏、北半球では日本のほか、欧州諸国でも記録的な猛暑に見舞われ、インド北西部で記録的な豪雨による被害が出ている。IPCCが再三指摘、警告してきた地球温暖化による極端な気象が顕在化している。一方、温暖化防止のための国際枠組み「パリ協定」による対策は遅々として進んでおらず、危機感は増すばかりだ。温暖化の一定程度の進行が避けられないのならIPCCや環境省が「適応策」と表する、人々の命や国土を守る対策の実行が一層強く求められている。
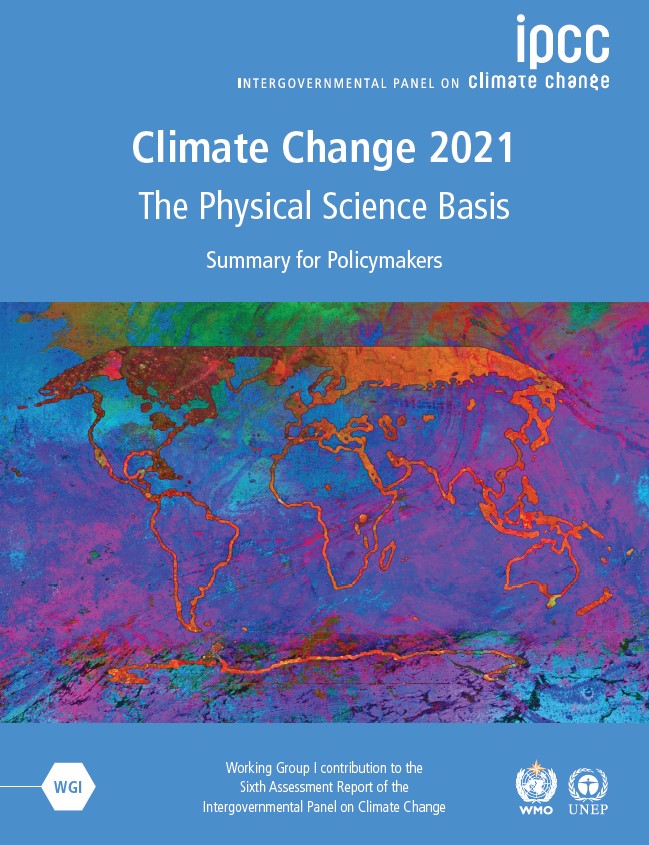
関連リンク




