大震災や感染症拡大、地球温暖化などさまざまな課題に直面する中、科学と社会をつなぐ科学コミュニケーションの重要性が改めて問われている。10月26・27日に開かれた「サイエンスアゴラ2024」の初日、科学技術振興機構社会技術研究開発センター(JST-RISTEX)が「科学コミュニケーションの現在と日本の課題」と題した講演会を主催。欧州の動向や日本の現状などを明らかにしながら、国内外の研究者と参加者が議論を交わした。

科学コミュニケーションとは、人々と科学者の交流・議論を促進するための考え方や活動のことで、日本では2000年代初頭に行政主導で導入された。現在、国内最大級のイベントであるサイエンスアゴラのほか、全国各地でさまざまな活動が展開されている。
講演会の冒頭、JST-RISTEXセンター長の小林傳司さんは、東日本大震災や新型コロナウイルス禍の際に、科学コミュニケーションに関する多くの議論があったことに触れつつ、改めて科学コミュニケーションにはどういう役割が求められているのか、国内外の研究者を招いて議論する機会を設けた、と趣旨を説明した。

大学や研究機関・科学者・政策立案者レベルで3つのトレンド
一人目の講演者は、伊トレント大学教授のマッシミアーノ・ブッキさん。ブッキさんは科学コミュニケーションに関する多数の著書・論文を出版している、いわば業界の権威だ。講演では、近年の科学コミュニケーション研究のトレンド3点が、自らの研究結果に基づいて紹介された。
1つ目は「大学・研究機関の科学コミュニケーション」。大学・研究機関が市民との対話であるパブリックエンゲージメントをどのように行っているかに関する国際的な研究で、実は国によって大きな違いはないことがわかったという。その上で、「大学や研究機関による科学コミュニケーションは、実際の研究成果の発信なのか、それともマーケティングを目的としたものなのか」との問題提起で締め括られていることを紹介した。
続いてのトレンドは「コロナ禍を通して社会的に存在感を強めた科学者」で、パンデミックは多くの科学者の露出と存在感を高めたという。この傾向は一層強まると予想されるため、より重視していく必要があるだろうと述べた。
最後は「政策立案者の科学コミュニケーションに関する意識」。英国、イタリア、欧州委員会の各指導者が、科学と科学コミュニケーションについてどう語ったかを比較した研究で、興味深い違いがあったという。英国は国家の誇りが科学と密接に関連していること、イタリアは名声だけでなくアイデンティティと満足度も与えていること、欧州は科学こそがヨーロッパたらしめている存在で統合の源泉にもなっていることを紹介した。

また、科学コミュニケーションの質を改善するには、正確性だけでなく文脈を理解すること、聴衆を理解することも重要であると強調した。加えて、科学者や研究機関の科学コミュニケーションスキル育成の必要性と、その責任を認識させることも課題として指摘した。近年の研究動向、未来へのビジョンが語られたブッキさんの講演は、科学コミュニケーションの現在を描き出すものだった。
フィンランドで研究室開放イベント、STEAM教育も
講演ではフィンランド・ユヴァスキュラ大学から2名の研究者が招かれ、同国における科学コミュニケーションとSTEAM(科学・技術・工学・芸術・数学)教育の実践的な事例について紹介があった。

10年以上フィンランドで生活している矢田匠さんからはまず、平等性に配慮したお国柄であるとした上で、その1つの表れとして教育カリキュラムについて紹介があった。同国は義務教育から博士課程まで学費が無料であり、高等教育では学生への補助も潤沢に用意されている。学びたいことに集中できる平等な環境が用意されているのだ。
続いて、フィンランドにおける科学コミュニケーションイベント「Researchers' night in Finland」が紹介された。研究機関の研究室を開放するお祭りのようなイベントで、今年は人口14万人のユヴァスキュラ市に1万5000人もの参加者を集めたそうだ。
このイベントは、研究者が自らの研究を題材に地域の人とコミュニケーションするために実施されているもの。ユヴァスキュラ市にある大型加速器の見学ツアーや、スポーツ科学の研究者が子どもたちと身体を動かすワークショップなどが催されていることが、好事例として紹介された。
続いてクリストフ・フェニベシさんからは、フィンランドにおけるSTEAM教育の事例が紹介された。科学、技術、工学、芸術、数学の5分野を統合的に学ぶSTEAM教育は、科学コミュニケーションとの親和性も高い。
まずフェニベシさんは「なぜ私たちは学ぶのか、なぜ人類は発展したいのか」との問いを投げ掛けた。さまざまな答えが考えられるとしつつも、世界のウェルビーイング(心身の健康や幸福)の実現に資することが重要だと主張した。実際に、電気すらも十分に供給されていない南アフリカ共和国の最貧地域におけるワークショップでは、数学とアートを融合させたことで、子どもたちの作品に政治的なメッセージが込められるようになるなど創造性が広がったという。

その上で、教育における重要な要素として、サステナビリティ(持続可能性)への意識、不確実な未来を切り開く能力(フューチャー・リテラシー)、地球人としての責任感(プラネタリー・レスポンシビリティ)をどう育成するのか、という点にも言及した。
魅力的なSTEAM教育の取り組みが、世界ひいては地球、という大きな視点を育む可能性が示されたフェニベシさんの講演は示唆に富むものだった。
人材育成へライティングスキル教育、キャリアパスの用意が不可欠
東北大学で広報・ダイバーシティ担当の理事を務める大隅典子さんは、科学者の立場から科学コミュニケーションに求めることについて、オンラインで講演をした。
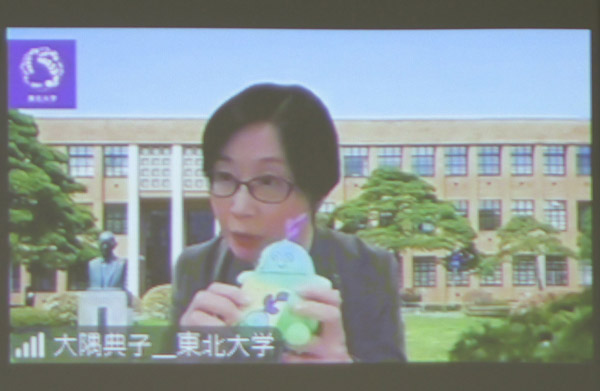
大隅さんは書籍やブログ、SNSを通して精力的に情報発信を行っている科学者。論文出版が科学者の基本的な科学コミュニケーションだとしつつも、一人ひとりが自分の研究や専門分野について、一般向け書籍やSNSなどで共有していくことが大切であると話した。
科学コミュニケーションをより推進するために大隅さんが指摘したのは、ライティングスキルの育成だ。識字率の高い日本では紙の新聞を読む人の割合が諸外国に比べて高いものの、科学面の扱いが小さいことを憂慮しており、その背景として読み手の少なさも関連しているだろうと考えを述べた。
その上で根本的な問題として指摘したのは、ライティングスキルを備えた人材の不足。特に日本の理系教育ではライティングの指導が不十分で、正しいことを正しく伝えるためのスキル教育が欠かせないと訴えた。
その他にも、行政に博士人材が少ないことや、女性研究者の割合が低いといった構造的な課題に加え、日本の科学コミュニケーション最大の問題として指摘したのがキャリアパスの問題だった。
約20年前に複数の大学に養成講座が置かれたものの、残念ながら姿を消してしまったものも存在する。人材育成のビジョンを再考するとともに、育てた科学コミュニケーション関連人材に多様なキャリアパスを用意することが必要だとした。大学経営者の顔を持つ大隅さんならではの視点で、さまざまな課題が共有された講演だった。
科学コミュニケーションのリスタートへ
質疑応答では、講演者と参加者の間で活発な意見交換が行われた。科学コミュニケーションの評価については、今後、科学コミュニケーションのピアレビュー(同分野の専門家による評価)が必要となってくるであろうこと、STEAM教育人材の確保には博士人材をより多く輩出するカリキュラムが求められること、多様な場で表現できる書き手を増やしていくことが科学コミュニケーション活動の一層の充実に繋がること、などが議論された。

閉会の際、司会を務めた東京大学教授の横山広美さんは、世界を、日本をより良くできる科学コミュニケーションはもっといろいろとあるのではないか、と講演を振り返って感想を述べた。また、行政主導で開催された意義に触れ、日本における科学コミュニケーションのリスタートとなるのではないか、という期待も語った。

科学コミュニケーションが日本で広まり始めて20年ほどが経過した。この間、サイエンスアゴラをはじめ、多種多様な科学コミュニケーションが日本各地で行われるようになった。しかし、科学コミュニケーションについて改めて考える、という機会は意外にも少なかったように思う。
国内外の関係者を招き、科学コミュニケーション自体について考える機会が設けられたことは貴重といえる。日頃はなかなか顔を合わせることのない、科学コミュニケーション関係者が知り合う機会にもなっていた。
関連リンク
- サイエンスアゴラ2024「科学コミュニケーションの現在と日本の課題」




