「『国際科学オリンピック日本開催』シンポジウム 〜池上彰さんと考える日本の科学ときみの未来〜」が8月22日、東京大学伊藤謝恩ホール(東京都文京区本郷)で開かれた。
主催したのは科学技術振興機構(JST)。主催側の「スポーツにオリンピックがあるように、科学にもオリンピックがある」という思いを掲げて国際科学オリンピックへの国の支援が始まって15年。国内選考に挑戦する生徒は2017年には2万人を超え、現在では毎年延べ31人の生徒が日本代表として7教科の国際大会に派遣されている。
「東京オリンピック2020」に合わせて複数の国際科学オリンピックの日本開催が計画された。2018年情報オリンピックが既に茨城県で開かれている。今後、2020年には長崎県で生物学、2021年に大阪府で化学、また2022年に東京都で物理、そして2023年には千葉県で数学、合わせて4つの国際大会が予定されている。いずれの大会も次世代をリードする優秀な若手が世界中から集まる。今回のシンポジウムは、これら国際大会の社会的認知や産業界からの支援の拡充を目指して、世界トップレベルの研究者やグローバル企業の経営者、若手オリンピアンたちを迎えて開催された。

シンポジウムの冒頭登壇したのは、2020年7月に開催される「第31回国際生物学オリンピック2020 長崎大会(IBO2020)」の組織委員会委員長の浅島誠さん。浅島さんは「2009年国際生物学オリンピックつくば大会から10年を経て長崎大会を実施できることは、日本の生物教育水準向上の好機だ」と開催意義を強調。大会コンセプトに“平和”を加えるなど、長崎らしい大会の実施を目指して世界80カ国から700人を超える生徒と引率者を迎える準備が進んでいることを紹介した。
「偶然は発明の父」
続いて登壇したのは、2012年にノーベル医学生理学賞を受賞した京都大学iPS細胞研究所所長・教授の山中伸弥さん。研究者の世界に進むことになったきっかけと道のり、そして新しい時代に向かう科学者の心構えを、小学生を含む幅広い層の来場者に、親しみやすい口調で語りかけた。
山中さんは、1988年当時まだ有効な治療法のなかったC型肝炎ウイルスで父親を亡くしたことをきっかけに、研究者への道を踏み出したことや、研究に没頭する中で、偶然が重なって人工多能性幹細胞(iPS細胞)を創り出すことに成功したことなどを紹介した。そして「研究は思いがけないことの連続」だとして、「偶然は発明の父」という言葉で講演を締めくくった。(講演詳細は:https://scienceportal.jst.go.jp/columns/highlight/20190904_01.html 関連記事参照)

立場・世代を超えて語られた新世代の科学の可能性
この日のシンポジウムでは、パネルディスカッションに最も多くの時間が費やされた。パネリストは、山中さんに加え、グローバル企業として次世代人材育成に力を注ぐアマゾンジャパン社長のジャスパー・チャンさんや、2005年に日本が初めて参加した第16回国際生物学オリンピック北京大会で銅メダルを獲得し、現在東京大学助教として研究の道を進む岩間亮さん、2019年7月フランスで開催された第51回国際化学オリンピックで金メダリストとなった栄光学園高校2年生の末松万宙さん。モデレーターはジャーナリストの池上彰さんが務めた。それぞれ年代も立場も違う5人が、国際科学オリンピックを軸に新しい時代の科学への向き合い方を語り合った。
チャンさんは、パネルディスカッションの冒頭の挨拶で、「アマゾンでは、社員一人ひとりがリーダーシップを発揮できるよう『リーダーの行動理念』を設けている。それがイノベーションの源泉になっている」と述べ、「毎日を“Day One”(始まりの日)と思い、何のための研究か、誰のためのイノベーションか、悩み続けることでイノベーションを生みだしている」とグローバル企業としての姿勢を紹介した。

令和の時代、科学はますます重要に
池上さんは、「偶然が重なり研究成果が得られた」と語った山中さんの話から、「この種の偶然を科学者はセレンディピティというが、研究を続けたからこそ巡り会えるもの」と、継続する大切さを指摘。「令和という新しい時代に日本の科学技術はどうあるべきかを皆さんと考えたい」とパネルディスカッションの趣旨を説明した。その上で「平成は日本の科学技術にとってどのような時代だったのか」と山中さんに質問した。

平成元年に研究医になることを目指して大学院に入った山中さんにとって、平成の30年間はまさに研究に没頭した時代だった。「克服できると思ったがんで未だに多くの方が亡くなっている。一方で自然が時間をかけて行っていたヒトゲノムの解析は一晩もあればできるようになった。30年のうちには予測できないほど革新的なことが起こり、倫理はますます大切となった。この令和の時代に何が起こるかは楽しみであり、怖くもあるが、資本主義社会を支えているのはイノベーションであり、その原動力として科学は欠かせない」。山中さんによると、科学は責任が重くなったからといって止められるものではないという。
ここでチャンさんは「イノベーションは生活の不便なところを解決し、豊かにするもの」とし、「日本の開発者はまだ世界をリードできていない」とグローバル企業のトップならではの厳しい意見を述べている。
岩間さんは、国際生物学オリンピックで初の日本代表になったことをきっかけに生物学分野の研究を進めている。「国際大会では、他国の生徒の物おじせずに発言する姿勢に圧倒された。共同研究の現場で積極に自分の意見を言う姿勢は、今も刺激になっている。自分の専門の生物学は、今や化学、物理、情報の素養なしでは研究できない。イノベーションには分野融合が必須だし、高校でも教科の壁を越えた授業をして欲しい」と若手研究者としての実感を語った。
国際化学オリンピック フランス大会の金メダリストとなった末松さんは、大会で出会った各国代表生徒たちの優秀さや、ご当地問題として出されたワインの成分を分析する実験課題の面白さなど、新鮮な体験を紹介した。「海外を見たことで日本が見えてきた」。国際科学オリンピック出場という経験を通して、日本と世界の違いを体感できたという。
こうしたやり取りに続いて「世界の科学技術の動向」と「日本の立ち位置」に関する資料が提示された。日本が一部の世界競争力ランキングで上昇しているものの、法人設立数が190カ国中106位と低迷しており、“起業が難しい国”ということを示唆している。また、国際的な論文の数が減るなど、今後のイノベーション創出に不安を感じさせるデータもある中で、日本政府が目指す「Society5.0」とはどのような社会なのかここで想像してみようということになった。
山中氏さんは「Society5.0の超スマート社会は誰もが幸せである社会、例えば、医療では、一人ひとりに最適な個別医療が提供されるようにならなくてはいけない」。チャンさんは「この30年のインターネットの発展によって、世の中の変化や競争は激化しているが、アマゾンの“人の生活を良くしたい”という姿勢は変わらない。それは、Society5.0になっても基本的に人間中心の社会だということに変わりはないということ」と、AIなどの技術はあくまでも人のためのものだと指摘している。
岩間さんは、Society5.0がいったいどのような社会なのか、正直よくわからないとしながらも「そうなっても、人との関係を大切にすることは変わらないで欲しい。スピードが問われる時代ではあるけれど、ゆっくり考えることで面白い発想が生まれることもあるので、じっくり考えることを支えてくれる社会であって欲しい」。
末松さんは、「AIに仕事を取られると恐れるのではなく、AIに任せる仕事と、人間がやる仕事の見極めが大事」という池上氏のコメントをメモしながら、Society5.0については、「好きなことに打ち込める社会になって欲しい」と率直な気持ちを語っている。

会場へメッセージ〜「科学する心」を育てよう
池上さんは、「2020年の東京オリンピック開催を控え、スポーツに注目が集まっているが、科学の世界でも生物学オリンピックなどが毎年開催されることに関心を持って頂きたい」として、「科学する心」を持ったパネリストたちに、会場へのメッセージを求めた。すると、山中さんは「子供の頃、『科学と学習』という雑誌があった。付録の実験セットが楽しみで、いつしか“科学する心”が芽生えたと思う。子どもたちに、どうやって科学の魅力を伝えるかがこれから大事になると思う」。チャンさんは、「これから20年、30年と、どう変化していくかとても楽しみだ。日本の技術者は知識も技術も優れている。あとは世界的な視野を持ち、自分の成功が、日本だけでなく世界のためにもなるという意識を持ってほしい」と会場の中高生にエールを送った。
岩間さんは、「当たり前のことを、疑ってみることが一番の科学だと思う。そして、他人と違うことを恐れないこと。それが研究には求められる」。末松さんは、「自分がここで貴重な体験ができるのも、大好きな化学を追究してきたからであって、みなさんにも自分の好きなことを納得のいくまでやってほしい」。それぞれ若い世代ならではのメッセージだ。
最後に、池上さんは、「好きだから、人と違ってもいいじゃないかとやってきたことが、結果的に日本のため世界のためになる可能性があるのが“科学(技術)”の素晴らしさ。ぜひ、若い方たちには、ここにいるパネリストを始め科学する人たちに続いてほしい」と締めくくった。
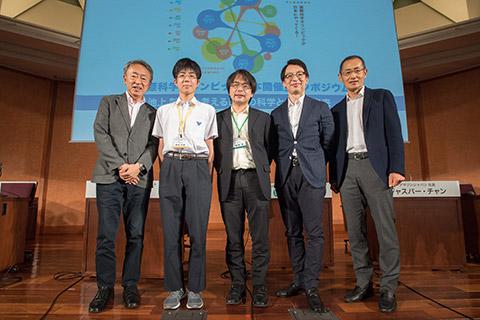
関連リンク




