
筆者は生まれつき、脳性まひという身体障害を持っており、電動車いすに乗って生活をしている。小児科医として10年ほど臨床経験を積んだ後、現在は障害や病気など何らかの困難を抱えた本人が、その困難の解釈や対処法について思考・実践する「当事者研究」という取り組みをテーマに研究や教育を行っている。ここでは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に触れつつ、誰ひとり取り残さないインクルーシブ(包摂的)なアカデミアや社会を実現する上で、当事者研究が持ちうる意義について紹介したい。
みんなを当事者研究者にしたCOVID-19
昨年末に報告されたCOVID-19は瞬く間に世界中に広がり、私たちの生活を一変させた。人類はいまだ、この想定外の出来事を理解し、対処するための十分な知識を持っていない。厳密にいえば、たった今、自分自身が感染しているのかどうかも定かではないし、自分を取り巻く身近な環境にどれくらいウイルスがいるのかも分からない日々を過ごしている。今、自分や世界がどのような状態にあるのかという基礎的な知識が揺らいでいるといえる。
さらに、私たちは誰しも、「これまでの私の人生はこのようなものだった」「これからの私の人生は、おおよそこのようになるだろう」という、人生に大まかな筋書きを与えるような自分だけの物語を持っているが、筋書きから大きく逸脱するCOVID-19のような想定外の出来事に直面すると、物語の継続が難しくなる。物語を未来に向けて書き進めていく作業は、過去を参考にしながら意思決定を重ねていくことに他ならないが、今の自分や世界に関する知識を失うと、日々の様々な決断が困難になる。
「今日、出勤しても良いのか」「買い物に行って良いのか」「少しくらいは外食を楽しめるのか」「少し体調がすぐれないが病院に行くべきなのか」など、以前は容易に判断できていたことが決められなくなることを、多くの人が経験しているだろう。短期的な意思決定だけではない。「仕事のスタイルを変えるべきか」「子どもの教育方針を変更するべきか」など、長期的な人生の見通しも揺らいでしまう。
私たちの知識や物語にアップデートを迫る逆境に対して、私たちは「研究」活動で応じる。例えば職業的な研究者は、ウイルスの性質、感染様式、病態を、文字通り研究し、ワクチンや治療薬の開発につなげようと日夜奮闘している。しかし、研究しているのはそういった職業的研究者だけではない。
今の自分や世界を理解するため、そして、日々の意思決定を行うために、メディアや書籍、インターネットで情報を得たり、自分と同じような困難を抱えている誰かに相談したり、実験的に新しい生活様式を始めてみるといった日々の活動もまた、先行研究の検索、観察、実験、対話を通じて、自らの知識や物語のアップデートを行おうとしているという面では、広義の研究ということができる。
筆者が専門にしている当事者研究とは、「自分が直面する困難や逆境に対し、自分や、世界や、他者との、直接的、間接的なやりとりを通じて、現実にかなったものへと自らの知識や物語をアップデートしようという取り組み」を意味する 。したがって、当事者研究とは新しい何かというよりも、昔から、想定外の困難に直面したときに私たちが当たり前に行ってきたことに他ならない。既存の知識や物語に沿うように自分や世界が作動している間は、私たちは当事者研究を行わなくても過ごせるが、COVID-19のような逆境を前に、私たちは否応なしに当事者研究者になる。
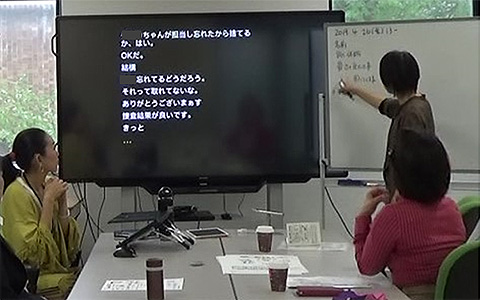
マイナーな苦労は「病理」か
ではなぜ、そんな当たり前の作業を、わざわざ「当事者研究」という名前で呼ぶ必要があったのだろうか。それは、広く共有され、ゆえに研究も豊富に蓄積されてきた「メジャーな苦労」と、一部の人しか経験しなかったり、経験していたとしても様々な理由で共有されなかったりしたせいで、ほとんど研究されてこなかった「マイナーな苦労」があるからだ。
人類が経験する苦労のレパートリーの一部——たとえば周囲の人には聞こえない声が聞こえるであるとか、周囲の人と異なる信念体系の中で生きる苦労など——は、勇気を出して周囲の人々に相談しても、それを聞いた人々に動揺を引き起こし、当たり前の対話が成り立たない状況がいまだに残っている。
こうしたマイナーな苦労は、地域社会の中で共に研究する対象ではなくて、共感することが困難な「病理」とみなされ、本人に対して精神障害などのレッテルが貼られ、病院など、特殊な施設で閉鎖的に取り扱われてきた。閉鎖的な環境で扱われるマイナーな苦労は、多くの人々の目に留まることなく対処される。そのために、地域社会の人々は引き続き、そうした苦労に対する忌避感や恐怖心を持ち続けることになる。
こうして、病院や施設に収容された当事者は、地域社会の人々とともに苦労の解釈や対処法を編み出していくという、当たり前の研究の機会を奪われ、研究作業を専門家に完全に委託せざるを得ない状況に置かれてきた。しかも少し前の専門家は、生物学的な専門用語を使って、当事者の苦労に対して過度に還元的な解釈を与える傾向があった。
最近になってようやく、当事者が公の場や書物などを通じて自身の経験を語る機会が増え、文字通り、研究を始めるようになった。その結果、症状がなくなることよりも、差別や偏見を向けられずに地域社会の中で尊厳を持って暮らすことが、当事者の思い描く回復像であるということが分かってきた。また、それを後押しするような知見として、幻覚や妄想といった症状が社会的排除の対象になるだけでなく、逆に社会的排除がこれらの症状を引き起こすリスクになるということも知られてきた。
しかし、まだ十分に、こうした苦労を抱える当事者を、共同研究者として包摂する社会が実現しているとは言えない。当事者研究という言葉は、こうしたマイナーな苦労を抱える当事者もまた、地域社会の中で当たり前に研究できる権利を取り戻せるよう、応援するために必要だったのである。
COVID-19による苦労の内容や程度には個人差
COVID-19は、ほとんどすべての人々に、大きな苦労を経験させた。しかし、その苦労の内容や程度には、個人差がある。例えば、一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティの調査によると、視覚障害のある人々が、「ソーシャル・ディスタンスを判断しにくい」「盲導犬は空いているスペースに入っていく習性があるので、ソーシャル・ディスタンスを取りづらく、気を使う」「情報を把握する重要な手段である『触れること』が困難になりつつある」などの苦労を抱えている。
また、聴覚障害のある人々も、「マスクをつけると聞き取りや読唇が難しくなる」「報道に十分な情報保障がついていない」などの苦労を抱えている。発達障害のある人々の当事者研究会「おとえもじて」も、「日常が崩れるストレス」「感覚が過敏でマスク・手洗いが苦痛」といった苦労を報告している。
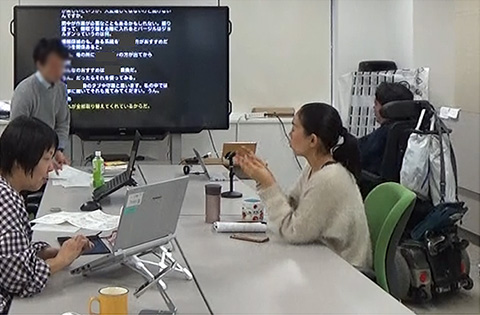
さらに、車いすで生活し、入浴や着替え、家事などに介助が必要な筆者自身は、「不特定多数との密で長時間にわたる身体接触が避けられない中、どのように感染予防するか」という新たな苦労を経験している。障害だけではない。経済的な理由や職業的な理由で、メディアから流れてくるメジャーな感染予防策を行えない人々は多く存在している。こうした苦労は、マイナーな苦労として共有や研究が不十分にしかなされていないが、有限な医療資源を集中的に投じるべき領域を判断する上では、マイナーな苦労を鋭敏に研究の俎上(そじょう)に載せ続けることが不可欠なのである。
ではどのような苦労がマイナーな苦労になりやすいだろうか。すでに幻覚や妄想、障害を例にして説明したように、少数派が経験する苦労や、隔離的な環境で対処されがちな苦労、差別や偏見の対象になりやすい苦労は、広く共有されにくいだろう。その他にも、「それは自業自得でしょ」と、自己責任として扱われやすい苦労もまた、オープンにしにくいものだ。そして、こうした苦労を抱えた人々は、社会の中で置き去りにされやすい。
当事者の研究者化と研究者の当事者化
科学コミュニティが、そして社会全体が、誰ひとり置き去りにしない、インクルーシブなものになるためには、様々な理由で共有されにくく、ゆえに研究が蓄積しにくい苦労を、積極的に研究テーマにしていく当事者研究のアプローチが不可欠だ。つまり、当事者の研究者化である。
加えて、科学者もまた、COVID-19によって新しい苦労に直面していることを忘れてはいけない。こちらは、研究者の当事者化とでもいうべき状況と言える。例えば、COVID-19流行期に科学研究をどうやって安全に継続させるかという苦労は、目下多くの研究室が直面しているものだ。一部の研究室では、実験の自動化や遠隔操作化が試みられている。こうした実験環境の変化は、筆者のように手が不自由な研究者にとって、研究環境がよりインクルーシブになりうる可能性を秘めているだけでなく、実験の再現性や透明性を高めるという科学における普遍的な価値をもたらしうるものでもある。
障害の有無を超えて、研究者一人一人が苦労を抱える当事者に立ち戻り、ともに当事者研究することで、アカデミアがよりインクルーシブで質の高いものになりうるのである。

熊谷晋一郎氏のプロフィール
1977年山口県生まれ。新生児仮死の後遺症で、脳性まひに。以後車いすでの生活となる。東京大学医学部卒業後、病院勤務などを経て2015年から現職。専門は小児科学、当事者研究。博士(学術)。著書『リハビリの夜』(医学書院、2009年)で第9回新潮ドキュメント賞を受賞。近刊は『当事者研究をはじめよう』(同、2019年)、『小児科の先生が車椅子だったら』(ジャパンマシニスト社、2019年)、『当事者研究』(岩波書店、2020年7月中旬出版予定)など。




