サイエンスアゴラ2019基調講演「A new generation of responsible science professionals for the New Age(新時代を担う新世代の責任ある科学者たち)」(2019年11月15日、科学技術振興機構主催)から―
人々の間で浮上する恐れと疑い

(日本語で)みなさん、こんにちは。サイエンスアゴラへのご招待ありがとうございます。何年も前に日本語を勉強しましたが、残念ながらほとんどのことを忘れていました。そのため、英語で続けなければなりません。
(英語で)さて、今回話をするのはブダペスト宣言20周年に関するもの、また、科学の社会的な責任です。欧州では複数の問題に直面しています。科学者また科学の専門家が、そして研究者たちがどうやって社会責任を果たしていくかについて、焦点が当たっています。
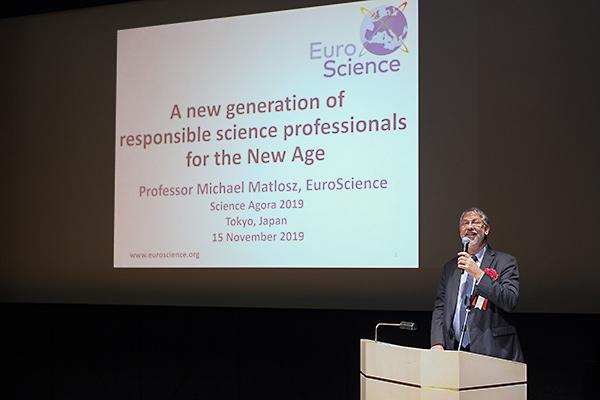
人間が新時代に入る中、欧州では国連の17のSDGs目標にコミットを表明しています。私たちは欧州の科学コミュニティーがもっと世界に貢献すべきだと思っています。近代の先進国やEUにおいては、おそらく人々は素晴らしい貢献が科学技術の領域から出てくるだろうと期待しています。
現実は常にそうした期待に応えているわけではありません。人々の間で浮上しているのは恐れと疑いです。科学の発見探求といっても、遺伝子、ナノ分子、AI、ロボットなどは安全なのか、害を与えるのか、それとも人々の職を奪うものになるのか、そうした疑問が呈されています。
そして、専門家は中立的なのか、信頼できるのか、利益相反を抱えていないか、不正はないのか、中立の一般的な人たちの利益を考えているのか、社会の発展に貢献しているのか、新しいツールやものをマーケティングして社会が求めないことを売り込もうとしていないか、公共の利益を考えているか、専門家をもっとコントロールすべきか、といったことが言われています。
「すぐに解決を」と科学界に圧力
次に「科学の自由」について問題提起します。欧州の伝統としては、特に学術界においては非常に強い自由がありました。社会が科学をもっとコントロールすべきでないかと求め始めると、私たち科学者は「それをどうやってできるのか」「今まで科学が達成してきたことを犠牲にせずにできるのか」と問い返します。
でもこれだけが課題ではありません。欧州や北米で起こっていることをみていると、合理的・妥当な議論をするのが困難になってきています。人々がとても感情的になっているからです。ごく限られた人しかエビデンスに注目を払いません。そして恐れや疑いを持つとともに、せっかちになってきました。
おかしなことですが、科学の発見はスピードアップしているのに、人々はすぐに問題を解決したがっています。これが科学界への圧力になっています。私たちはどう対応すればいいでしょうか。科学のコミュニティーは危機に直面していると言えます。気づかない人もいますが、それは認知していないからであり、困難はひどいものになりつつあります。

「信じてください」では困難に
欧米では基礎研究は公的資金でまかなってきましたが、その源泉は国家の税金です。それは民主主義によって担保されていました。しかし、選挙の重要性を考えてください。ポピュリズムの政府が欧州で選ばれるようになり、科学者が説明責任を果たすよう求められる機会が増えてきました。
これまで、科学者は科学を、専門家は専門を、その結果がどうなるかあまり気にせずに仕事してきました。公的資金による研究にはだいたい自由度があり、説明責任は非常に限られていました。それがここ数年は変わり、かなり深刻な問題を呈しています。
私たちがやらなければいけないのはパラダイムシフトです。もし何かミスがあって個人が非難されるようなことがあっても、科学の価値が損なわれない社会にしていくことが大事です。社会的責任を持つのか、それともあるいはある基準に基づいた専門家としての責任を果たしていくのかという話です。いままで科学者、学術者は政策のところで例外とされていた。なぜならば研究者を信じていたからです。やっている研究が長期的には有益だろうと考えられていたからです。
しかし基礎研究の科学者と話してみてください。遺伝子操作、またはロボティクス、AIの研究をしている人に「ちょっと心配なんだけど」というと、科学者はどう答えると思いますか? 「信じてください」というはずです。でも、お金をくれたならちゃんとやりますよ、というやり方は将来なかなか難しくなるでしょう。

透明性や多様性を高めたい
近代の科学界は例えば物理学者であったなら、生物学者とコミュニケーションをとりません。生物学者なら金属学者とは話しません。21世紀の科学は複雑になり、学際的なものが必要になってきました。社会責任の一部を担うようになり、学際を超えたピアレビューが必要になってきます。それができるパラダイムはありません。でも、そうはいっても、科学者は基本的にオープンで研究の自由さなどを失いたくはないです。オープン・探求的・専門的で興味に沿った科学的研究はそのまま継続したいと思います。
では欧州で何をしようとしているのでしょうか。まずオープンアクセス、オープンデータ。これらは国際公共財として広く活用されるものと見られています。しかも途上国が不利にならないようにしたいです。
合理的な不確かさ、間違いもある程度許容したい。間違いは詐欺、ごまかしではないからです。利益相反も認めたい。すべての人は何らかの形で矛盾を持っているので、透明性や多様性、包摂性も高めたい。ジェンダーバランスやさまざまな形の差別をなくし、ピアレビューには何らかの形で市民に関わってもらいたいと思っています。

未来は若手科学者にかかっている
ユーロサイエンスは3000人のメンバーがいて、科学のプロとして所属機関とは別に個人参加しています。それぞれが個人として科学を見ており、科学のあり方を変える必要があると考えています。科学に対する信頼は当たり前のものではなく、確立していかなければなりません。社会の声をすくい取る必要があるので、サイエンスアゴラやユーロサイエンスオープンフォーラムのようなイベントは、オープンな議論をする場として重要です。この分野の変化は簡単ではなく、科学界だけに限定して変化を追求してはいけません。
未来はやはり若手科学者にかかっています。その才能を育てるようにすべきです。キャリア開発の機会、よりよい労働環境、幅広い研究のアセスメントを構築し、ミスで責任をとったからといってキャリアが犠牲にならないようにしたいです。
若手の基本的なスキルを開発するのに、サイエンスアゴラは役に立っています。オープンで好奇心に基づく対話を生み出しているからです。昔のパラダイムで一番大事なのは当該分野の学者に認められることでしたが、これからは科学界を超えていかなければなりません。

マイケル・マトローズ 氏プロフィール
ニュージャージー工科大学で化学工学の理学士号、カリフォルニア大学バークレー校で電子化学工学の博士号を取得。1985年にスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)材料工学科で研究者としてのキャリアを始める。1993年、フランスのナンシーにあるロレーヌ大学の化学プロセス工学教授に就任した。2014年から2017年まで、パリのフランス国立研究機構(ANR)理事長兼最高運営責任者。2011年にフランス技術アカデミー会員に選出。欧州の研究実施機関および研究助成機関が加盟する支援団体、サイエンス・ヨーロッパ(本部ブリュッセル)の会長も務めた。現在はロレーヌ大学の特別教授(化学工学)で、2018年7月から4年の任期でユーロサイエンス(欧州科学技術推進協会)の会長を務めている。
関連リンク




