地球から131億光年離れた宇宙のはるか彼方で2つの銀河が合体している証拠を捉えたと、早稲田大学や国立天文台などの研究グループが発表した。これまでの銀河合体の観測例としては最も遠いという。南米チリにあるアルマ望遠鏡の観測データを分析した成果で、研究論文は18日付「日本天文学会欧文研究報告」に掲載された。
研究グループには、早稲田大学理工学術院の橋本拓也研究員、井上昭雄教授や東京大学宇宙線研究所の馬渡健 ICRRフェロー、名古屋大学の田村陽一准教授のほか、国立天文台、大阪産業大学、大阪大学、京都大学などの多くの研究者が参加した。
今回観測対象となった天体は、ろくぶんぎ座の方向にあり、地球から131億光年も離れた「B14-65666」。米国のハッブル宇宙望遠鏡の観測により、この天体には2つの星の集団があることが分かっていた。橋本研究員らはアルマ望遠鏡の観測データを詳しく調べた。
その結果、この天体にある酸素や炭素、小さな粒子(ちり)が放出した電波を検出することに成功。天体には2つの銀河があり、いずれも地球からの距離、大きさはいずれもほぼ同じで、隣り合う2つの銀河は異なる速度で動きながら互いに衝突し合体しつつあることを突き止めた。この天体は太陽系が属する天の川銀河の約100倍のペースで星を生み出していることも分かった。合体によって銀河のガスが圧縮され、爆発的な星形成が起こったと考えられるという。
宇宙誕生は約138億年前とされている。その時に宇宙に存在した元素は水素とヘリウムだけだった。研究グループの説明によると、これまでの研究から宇宙誕生後2〜3億年経過したころに最初の星が作られたと考えられている。星の中では水素をヘリウムに、ヘリウムを炭素や酸素に変換する核融合反応が進み、さまざまな元素が生み出されている。
星が一生を終えるときに超新星爆発を起こすが、その時に元素が宇宙にまき散らされ、まき散らされた元素の一部は、結びついてちりを作る。こうした元素やちりは宇宙空間に漂うガスと混じり合い、次の星の“材料”となる。このため、宇宙の初期の時代の酸素や炭素を見つけることは、それよりさらに前の時代の星の誕生と死を知る手掛かりになるという。
今回研究グループは、宇宙の誕生から約8億年程度という古い宇宙の時代の銀河合体を捉えた。井上教授は「これほど遠方の銀河からの酸素、炭素、ちりが放つ電波を初めて全部揃って検出できたのは快挙と言える。今後さらに窒素や一酸化炭素分子を検出し、銀河の形成と進化などの解明を目指したい」とコメントしている。

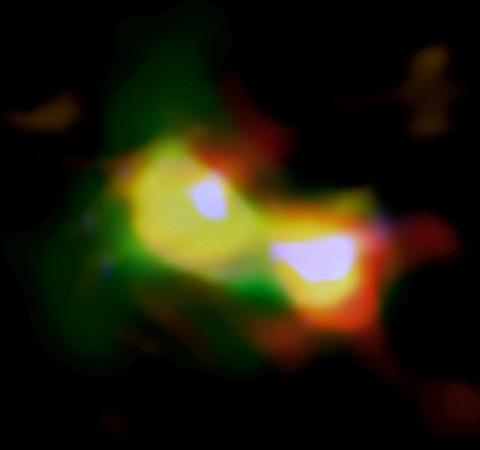
関連リンク
- 早稲田大学プレスリリース「観測史上最遠の合体銀河の証拠」
- 国立天文台プレスリリース「アルマ望遠鏡、観測史上最遠の合体銀河の証拠をとらえた」




