江戸時代にはさまざまなからくりが作られていました。言葉でみても、当時の書物や興行ちらしには、からくり、カラクリ、絡繰、操、唐繰、機関、機巧、巧機、機、旋機、機捩、関捩、関鍵、器械など、多くの文字が出てきます。西欧から伝わった「のぞきからくり」や「龍吐水」、「エレキテル」、「時計」などもからくりとして見せ物や売り物になっていました。

科学的、技術的な理屈はともかく、何らかの機構を持って動く物や、種々の工夫を凝らした物が「からくり」として捉えられていたのです。ここでは、ロボットの原型としてのからくりについて整理してみましょう。
まず、からくりが作られる対象から分類すれば、
-
祭礼、神事のために作られたからくり
代表的なものとして、台車、山車からくりなどと呼ばれるものがあり、室町期に完成された京都舁山の不動の立居人形を祖として、各地に広まった。現存するものも比較的多い。
-
芝居などの一般大衆への見せ物として作られたからくり
竹田からくり芝居のようにからくり自体を見せ物としたものや、人形浄瑠璃のように舞台面における演出装置として使われたもの。常時使用されるため当時のもので現存するものは少ない。特にからくり芝居などにおいて、商品価値のなくなったからくりは保存されない場合が多く、ほとんど残されていない。
-
おもに個人を対象に作られたからくり
商品としてのからくり人形や、特定個人のために作られたからくり人形がある。個人の所有のため、残っているものもあるが、現代のおもちゃと同じに壊れて捨てられることが多く、現存数はそう多くない。
また、その仕組みや構造から、2つに分類できます。
- 内部に機関を持ち、原動力は弾性ばね(鋼、真ちゅう、鯨のヒゲ、竹など)水、砂、空気、水銀などによって人形を動かす。
- 原動力は人力により、糸や串を手などで操作し、仕掛を見せる事なく、さながら機関で動くように見せかける。
日本のからくりの特徴は、誰でもが祭りや見せ物、商品としてからくりを身近に見たり買ったりでき、その状況の中でからくりが発展したことがあります。しかし仕組みや構造から見れば、同時期の欧米とくらべて、日本のからくりははるかに遅れていました。特に絶対的に劣っていたのが動力技術です。
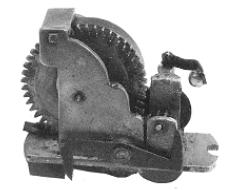
金属製のゼンマイは当時の日本ではほとんどできない状況でした。いくつかのゼンマイからくりが作られましたが、鯨のヒゲを使った茶運び人形は大きさや強度の制限があり、「飛蛙」のような金属ゼンマイ製のからくりは江戸時代のマイクロロボットとして作られました。
逆に言えば、この遅れが、長短ある日本のからくりの知恵と技を育んだ大きな特徴でもあるかも知れません。「弓射童子」も動力を使う目や口の動きではなく、能面のような人形の顔の素晴らしさで表情を出そうと考えたふしがあります。
このような「もったいない」は、からくりにもたくさん見られるのです。日本のからくりは、限られた条件、制約の中で、大衆のために職人たちが生み出した知恵と技の固まりなのです。
本サイトに掲載されている記事・写真・図表・動画などの無断転載を禁止します。

鈴木一義(すずき かずよし) 氏のプロフィール
専門は科学技術史で、日本における科学、技術の発展過程の状況を調査、研究をしている。特に江戸時代から現代にかけての科学、技術の状況を実証的な見地で、調査、研究をしている。
これまでに、経済産業省「伝統の技研究会」委員、大阪こどもの城、トヨタ産業記念館、江戸東京博物館、その他博物館の構想委員や展示監修委員などを歴任。

古田貴之(ふるた たかゆき) 氏のプロフィール
独立行政法人 科学技術振興機構 北野共生システムプロジェクトのロボット開発グループリーダーとしてヒューマノイドロボットの開発に従事。2003年6月より千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター所長。2002年にヒューマノイドロボット「morph3」、2003年に自動車技術とロボット技術を融合させた「ハルキゲニア01」を開発。




