この[シリーズ]では、諸外国の製造業強化のための研究開発戦略や政策をレポートする。第1回で取り上げるのは、“競争力のある小国”シンガポール。生活用水や産業用水など、水確保のための研究開発をご紹介する。
シンガポールの水事情
日本には「湯水のように使う」という表現がある。お金等の貴重な物をあるに任せて「湯水のように」乱費することの例えである。この表現では、水は掃いて捨てるほど大量にあるが故にそれほど価値のないものの代表として扱われているが、シンガポールではこの表現は全く逆の意味として理解されるかもしれない。
シンガポールは、ほぼ赤道直下、東京23区と同等の面積約710平方キロメートルの島に約520万の人々が高密度にひしめいて生活する都市国家である。気候区分は熱帯雨林気候に属し、雨期にはバケツをひっくり返したようなスコールと激しい雷雨が1日に何度も訪れることも珍しくなく、乾期であっても結構な頻度で雨が降る(事実、年間降水量は日本の約1,700ミリを上回る2,400ミリ)。このため、水も「湯水のように使う」ほど豊富なのではないかと思われているかもしれないが、事情は全く逆である。
シンガポールは国土の狭さ故に、その降雨を十分に貯蔵する地域が限られており、また、大きな河川、天然の帯水層や地下水も存在しないことから、人々が生きるために必要な飲料水等の生活用水、および工業化に必須の産業用水という「資源としての水」をいかに確保するかは、シンガポールにとって独立以来文字通り死活問題であった。
シンガポールでは、水は「湯水のようには使えない」貴重品なのである。
人は水がなくては生きてはいけない
1942年、日本軍がシンガポールを攻略した際に、マレーシアからの水源を遮断して英国軍を早期に窮地に追い込んだことは、リー・クアンユー初代首相がシンガポールの水の脆弱(ぜいじゃく)性を再認識したきっかけとなったという。また1965年の分離独立時にマレーシア政府がシンガポールへの水供給打ち切りをちらつかせ水取引を外交的圧迫の手段に使おうとした行動も、国の安全保障として一刻も早い「水の独立」の必要性を認識させることとなった。
極端な例えだが、「人は石油なしでも生きられるが、水がなくては絶対に生きられない」ので、シンガポールでは建国以来、国を挙げて「水の独立」に向けた法整備、制度整備、インフラ構築、そして研究開発が着実に進められてきた。
現在、シンガポールにおいては、「4つの蛇口」と呼ばれる水の供給源がある。
- 雨水:効果的な都市設計による効率的な雨水の収集とその貯蔵システム
- 輸入水:期限付き売買契約に基づくマレーシアからのパイプラインによる水購入
- 再生水:“NEWater”ブランドで知られる排水等の再処理水
- 海水淡水化水:海に囲まれたシンガポールの豊富な海水を利用した脱塩淡水化水
2011年のデータによると、全供給量のうち、ある意味不安定な気象的・政治的状況に左右される供給源である雨水と輸入水を合わせた供給の割合が60%と過半を占め、残りは再生水30%、海水淡水化水10%となっている。
一方、再生水、海水淡水化水は自らの研究開発への注力によって確実に供給量を増加できる要素である。そのため、安定的な水の供給確保に向けて、シンガポールでは輸入水の契約が切れる直前の2060年までにそれぞれの供給量(ちなみに、2060年の供給量は2011年の2倍になると試算されている)の比率を55%と25%(合わせて全供給量の80%)まで高めることを目標に、内外の産学官の力を結集した研究開発を積極的に促進しているところである。
官学産一体による研究開発
2006年、政府は環境・水関連産業分野の研究開発促進のため、5年間で3億3千万シンガポールドル(2011年にはさらに1億4千万シンガポールドルが追加配賦され総計4億7千万シンガポールドル)の国家予算を割り当てることとなった。

PUB資料「Ensuring Water Sustainability in Singapore」より抜粋
これらの資金を政府の指針に応じて効率よく運用し、水関係産業開発を包括的に主導することを目的として同年5月に設置されたのが「環境・水関連産業開発評議会(EWI:Environment & Water Industry)」である。
EWIは行政的には公益事業庁(PUB:Public Utility Board)に属するバーチャルな組織で、各種の主要な環境・水関連産業発展に係る政府機関、例えば経済開発庁(EDB:Economic Development Board)等の資源や人材を有機的に活用できる。EWIの統合指揮の下、官学および産のさまざまな機関が協力しつつ政府一体として水関連産業推進政策を効率的に実践するのである。
EWIはその活動方針として、
- 外国企業の誘致や地元企業の育成によるクラスター形成
- 研究開発支援や人材育成による研究能力開発
- 政府主導による水関連産業輸出支援やブランディング推進によるローカル企業の国際化
の3つを掲げ、それに基づきシンガポールにおける水関連産業の育成と研究開発を支援するが、ここでは特に(2)の機能に注目したい。
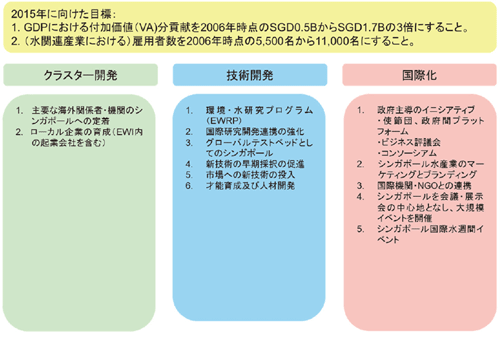
PUB資料「Ensuring Water Sustainability in Singapore」より抜粋
EWIでは、研究能力開発の実践に資する6段階の戦略を定め、それらを支援するためのさまざまな支援スキームを用意している。すなわち、基礎研究、応用研究段階を支援する第1戦略として「環境・水処理研究プログラム(EWRP:Environment & Water Research Programme)」(=後述)、新技術の早期採択を支援する第4戦略として「TechPioneer」(=デモンストレーションやパイロットプラント試験を通じて企業による新技術や革新技術の早期採択を促すためのプログラム)、市場への新技術投入を支援する第5戦略として「Fast-Track Environmental and Water Technologies Incubator Scheme (Fast-Tech)」(=スタートアップ企業の環境・水技術の産業化を支援するためのインキュベーションファンド)、そして第6戦略として才能育成、人材開発促進のための「EWT Graduate Scholarships」(=環境・水分野における研究リーダーの育成のために4年間までの博士課程履修を支援)等である。
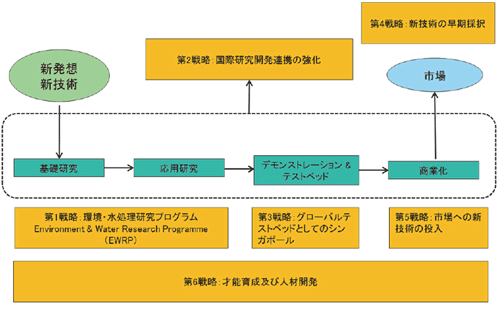
PUB資料「Ensuring Water Sustainability in Singapore」より抜粋
環境・水処理研究プログラム(EWRP)
EWRPは、環境・水分野において国の政策に沿った研究開発を推進するための競争的ファンディングプログラムである。
EWRPでは、大学・公的研究機関または私企業にかかわらず物理的にシンガポールに居を置く機関に対し、基礎から応用までの幅広いイノベーティブな研究課題の実施への資金援助が可能であるが、支援を得るためには最終的に産業化の道筋が視野に入れられている必要がある。
EWRPには下記の2種類の支援スキームがあり、公的機関は費用の100%、私企業は70%を支援される。
- イノベーション開発型(IDS:Innovation Development Scheme)
シンガポールに拠点を置く私企業に対して応用研究にかかる資金を一部支援する。公募の時期を定めず随時支援申請を受け付けるもの。 - 研究・イノベーション インセンティブ型(IRIS:Incentive for Research & Innovation Scheme)
競争的プロセスを経て公的研究機関、大学等高等教育機関、私企業に対する研究資金支援を実施する(2006年以来これまで計15回の公募が実施され、現在82課題を支援)。
弱点を強みに
これらの官学産による積極的な研究開発支援の結果、現在では水研究においてシンガポールの研究機関が世界のトップ1、2位の評価を得るまでとなっている(2013年ラックス・リサーチ)。
弱点であった「水」は、今やシンガポールの強みとなったと言えよう。
「産学官連携ジャーナル」の記事を一部改変


