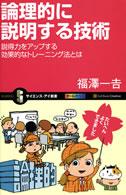|
日常での会話のやりとりを冷静に観察してみると、必ずといってよいほど「やっぱり」という表現を耳にする。何が「やっぱり」なのかと、心の中で思っていても、なかなかそれを言い出せないことも多い。口癖レベルで多用される「やっぱり」は、有意な議論を深めることを阻害していると感じる人も少なからずいるのではないだろうか。
表現として「やっぱり」が登場するためには、本来、以下のような流れが必要であると著者はまとめている。ある事柄に対して、それをいったん否定するような仮説を用意し、それを検証し、その結果としてその事柄への支持を“あらためて”表明する、というものである。
そこで、こんな例を考えてみた。「やっぱり、仕事の終わりにはビールが最高だよな」と、居酒屋で同僚から唐突に声をかけられたとする。それには、仮説(アルコールでない方がよい)も、検証(ある理由からアルコールである方がよい)もあるわけではないので、あなたはひとまず「うん」と同意することになるだろう。つまり、本書の解説によれば、このような「やっぱり」は、解釈上の共犯関係に取り込み、自分の主張と相手の意見とのぶつかり合いを避けようとする話法にすぎないのだという。
なにも、飲み物の嗜好(しこう)に関するやりとりぐらいであれば、目くじらをたてることはない。しかし、本書後半に登場する例、「やっぱり、政権交代は国民が望んでいたものだ」のような主張に出合ったときは、慎重になるべきだ。「何が“やっぱり”なのだろうか」という直感的な感想、すなわち「明示されていない内容は何か」という疑問が、ここで重くのしかかる。つまり、この主張の前後を読んでも、裏付けとなる「論拠」がない可能性がある。
その状況を、良く解釈すれば「互いに暗黙の了解が確認できている」となる。あえて厳しく言うならば、意図的ではなくとも「理由がはっきりしない」ままであると思われる。後者の用途として「やっぱり」と同様に無意識に使われている表現、「じゃないですか」「っていうか」「みたいな」などのことを、著者は“心理的緊張回避語族”と名付けている。
「以心伝心」という用語がある。これは、言葉を使った意思表示をしなくても気持ちがお互いに伝わるという、日本独特のコミュニケーション方法を指す。この以心伝心の対岸にあるのが「KY(空気が読めない)」になるだろう。その場の空気を読むことが効率のよいコミュニケーションをもたらすとはいえ、それは言語に頼らないが故に読み違いが起こり得る、危ういスタイルであることに気付かされる。
本書は、見開き2ページに1つのトピックをレイアウトする形式の、手に取りやすい新書だ。にしかわたく氏のカラフルなイラストもふんだんに添えられている。気になるページをぱらぱらとめくるだけで、「根拠と論拠」「論理」「論証」など、あらためてその違いや定義を尋ねられてもうまく答えられないような術語の勉強になる。また、英国の分析哲学者・トゥールミンの議論モデルの解説も明快だ。
「論理的に説明する技術を身に付けるには、“やっぱり”この本が一番だ」。本書を読むことで、この主張への論理的な解説がきっとできるようになるだろう。