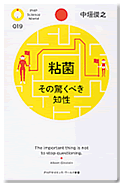|
粘菌といわれて、何を思い浮かべるだろうか。研究者としての南方熊楠、宮崎駿アニメの「風の谷のナウシカ」、マンガでは「もやしもん」…。最近注目を集めている漫画家の水木しげるの熊楠の半生をつづる「猫楠」でも、粘菌は登場する。森の中の木の表皮にべったりとへばりつき、時には数メートルにもなりながらも一つの細胞である不思議な印象を持たせる粘菌。これに、また脚光を浴びせたのが、2000年9月にNatureで「粘菌の知性」を発表した著者の中垣俊之氏らのグループだ。
粘菌の変異体が寒天ゲルの迷路の上を出口と入り口の餌に向かって最短ルートを探りながら進む写真は、非常に印象深い。粘菌とは、細胞壁を持たない不定形の原形質の塊だ。もちろん、脳や神経系を持たないのだが、迷路の中を、まるで知性を持ち自分で判断しながら、ゴールに向かって進んでいるかのように見える。本書では、粘菌の特性や育て方から始まり、この粘菌の動きをさまざまな条件の下で調べ、ひたすら観察した様子を示している。餌を置く場所や数、粘菌の量と餌の量比、粘菌が嫌う条件を加えるとどうなるのか、関東圏の地図を描いた寒天プレートの上に餌を置いて、交通網を作らせたらどうなるのか。著者らが次々に繰り広げた実験を、わくわくしながら読み進めていくことができる。
原形質の塊というこの「物っぽい生き物」に脳や神経系があるのでは、とつい錯覚してしまう。全体を総括して指令を出す司令官がいるわけではないが、それでも全体の行動がうまく整っていく。粘菌は、いわゆる自律分散方法をとっているが、実は、これはいかにも生物らしい問題の解決法だという。著者らは、さらに粘菌の迷路の解決方法をコンピューターで計算し、数理モデルを構成した。この数理モデルを使って粘菌の動きを再現することで、カーナビや都市間交通のネットワークデザインに応用できるという。さらに、さまざまな観察から判明した、粘菌の判断能力や学習能力から、「知性とはなにか」という根本的な問題に迫ることへの可能性を示している。
この研究には、2008年にイグ・ノーベル賞(認知科学賞)が贈られた。裏ノーベル賞ともいわれるが、なかなか表舞台に立ちにくい研究を世間に知らしめ、科学のおもしろさを再認識させる狙いもある賞だ。Nature発表以来、国内外のテレビや新聞、雑誌などで何度も紹介され、特に、イグ・ノーベル賞の受賞前後には、国内のメディアにも何度も登場したので、記憶にある人も多いかもしれない。また著者は、一般市民や小中高校生対象のイベントにも参加し、粘菌の研究を通して科学コミュニケーションを図る活動を積極的に行っている。自分たちの研究を「すき間産業」と言い、身近なところにたくさんのフロンティアが存在すると謙虚に語る著者が、これまで行ってきた十数年の研究を、今後の展望も含め非常にわかりやすく表現している。