皆さんは、テレビやインターネットで野生動物のコンテンツを見て、心が動かされた経験はないだろうか。画面の向こう側に映る力強さ、繊細さ、時にはかなく見える姿。メディアを通して知った、厳しい野生の世界で生きるさまに心を奪われ、彼らのことをもっと知りたくなって研究者を目指すことになった。しかしメディアは、野生動物にとって好ましくない状況を生むこともある。私たち一人ひとりにできることは何かを考えたい。

増えるよりも速い取引が野生動物を絶滅に追いやる
テレビには、時に人生を変えるほどの力がある。最近も、ボツワナの野生動物を扱ったドキュメンタリー番組をきっかけにリカオン(アフリカに生息するイヌ科の動物)の研究者を目指す高校生から連絡があり、メディアが夢や希望を与える力を改めて感じた。しかし、私たちが目にする野生生物の描かれ方が、知らず知らずのうちに彼らを危険な状況に追いやることもある。

「持続可能ではない野生生物取引」という言葉を聞いたことがあるだろうか。簡単に言うと、野生の生き物たちが自然の中で子どもを産み増えるスピードよりも速く、人間が彼らを採取したり捕まえたりして、取引されることだ。
この取引は、ペット飼育はもちろん、飾り物、食べ物、薬の材料など、いろいろな目的で行われている。爬虫類、鳥、ほ乳類、魚、昆虫など、対象はさまざまだ。
何かのきっかけで人気が出ただけで、あっという間に自然の中から姿を消してしまう動物もいる。SNSやテレビで人気が急上昇したコツメカワウソはその典型で、ペットとしての需要から密輸が横行し、国際取引が原則禁止されるほど野生での数が減ってしまった。また、動画サイトなどで見られる愛らしい姿によって生態が誤解されたまま人気となった霊長類のスローロリスも、ペット目的の違法な捕獲や取引によって、野生での生存が脅かされている。
こうした捕りすぎが、多くの野生生物を絶滅の危機に追いやる大きな原因になっているのだ。自然界のバランスを崩し、外来生物の問題や、新しい感染症が広がる危険までも大きくする。

光が当たりにくい違法取引の「需要側」
特に問題なのが、違法な野生生物取引だ。薬物や武器の密輸にも匹敵すると指摘されるほど巨大な違法市場を形成しており、象牙を目的としたアフリカゾウの密猟のように、組織化された犯罪グループが関与しているケースも少なくない。
インターポール(国際刑事警察機構)が2023年に133カ国と連携して行った野生生物の違法取引に対する一斉摘発では約500人が検挙され、絶滅の恐れがある種を含む2100件以上の動植物が押収された。インターポールの事務総長は、これらの犯罪の多くが「暴力、汚職、金融犯罪などの国際組織犯罪グループと強いつながりがある」と指摘しており、その根深さを物語っている。海外では「アルバイト」感覚で勧誘された若い日本人が希少動物の運び屋として利用され逮捕される事例も報告されている。その背景には、日本を含む先進国など、買う側の国々からの強い需要があることが分かっている。

ワシントン条約などの国際ルールや各国の法律による取引規制は存在するが、密輸や法の抜け穴を突く取引は後を絶たない。また、規制はどうしても「供給側」(捕獲や密輸をする人)への対策が中心になりがちで、その根本にある「需要側」、つまり、欲しがる人や利用する人の問題には、なかなか光が当たりにくいのが現状だ。
需要を刺激するメディアの影響力と責任
では、野生生物を「欲しい」「買いたい」という気持ち(需要)は、どこから生まれてくるのだろう。 その背景には、私たちの日常に深く入り込んでいる「メディア」の影響があることが、研究や専門家によって指摘されている。
これは「メディア・フレーミング」とも呼ばれ、メディアが特定の情報(例えば、動物のかわいらしさや珍しさ)を強調したり、逆に一部の情報(飼育の難しさや生態系への影響など)を伝えなかったりすることで、私たちの生き物に対する印象や認識が無意識のうちに形作られていく現象を指す。
テレビ番組、映画、インターネット動画、SNS、広告などで珍しい動物が愛らしく描かれたり、簡単に手に入るかのように紹介されたりするのも、その一例と言えるだろう。結果として、「触ってみたい」「飼ってみたい」という気持ちが刺激されることがあるのだ。
もちろん、情報を受け取る私たち自身の知識や判断力(メディアリテラシー)を高めていくことも非常に大切だ。しかし、それと同時に、情報の発信源であるメディアが持つ大きな影響力と、その発信に伴う責任も忘れてはいけない。メディアでの動物の扱いが時に視聴者から批判を受け、いわゆる「炎上」につながるケースも少なくない。
例えば、希少動物をペットのように見せる演出が「安易な飼育を助長する」として視聴者や専門家が強く批判し、番組に協力していた動物園からも抗議の声が上がった事例がある。ある人気番組が生態系に関する誤った情報を発信したとして専門家から指摘を受けたり、特定の地域で実施した希少種捕獲のロケ企画の内容が問題視され、地元議会が放送局へ公式な抗議文を送付したりしたケースも報じられている。タレントが動物園の飼育エリアに落下し、動物への配慮や安全管理のあり方が厳しく問われたことも記憶に新しい。
表現内容や動物への配慮の監修、リテラシー研修を実施
こうした現状から、私は「需要」に影響を与えるメディアの役割に着目した。本来メディアには、人々の価値観を動かす素晴らしい可能性がある。そこで作り手であるメディア企業やクリエイターの方々と連携し、表現を通じて自然への敬意や共感を育むことができれば、社会を良い方向に動かせると信じ、「ROOTs(Rooting Our Own Tomorrows)」を立ち上げた。メンバーには動物福祉に詳しい法獣医の専門家、生き物の研究に情熱を燃やす学生、ビジネスの視点を持つコンサルタントなどが名を連ね、それぞれの知見を共有しながら活動している。
ROOTsでは主に二つの取り組みを行っている。一つは「クリエイティブ・サポート」だ。テレビ局や制作会社、広告会社などに対して、野生生物に関する専門的な情報を提供したり、表現内容が誤解を招かないか、動物への配慮がなされているかなどをチェックする監修サービスを行ったりするほか、社員全体のリテラシーを上げるための社内研修やガイドライン導入を実施している。
例えば、私はTBS系列のドラマ『Eye Love You』で、ラッコをはじめとする登場動物に関する監修を実施した。主な役割は、研究室の雰囲気、研究対象となる動物種の選定、彼らが置かれる状況設定など、リアリティを高めるため物語の土台となる設定段階からアドバイスをすること。さらに台本においては、動物の描写が生態学的に正確であるか、そして誤解を招いたり不適切だったりする表現が含まれていないかを細かくチェックした。
作品の向こう側にある「命」への想像を
もう一つが「クリエイター・パートナーシップ」。クリエイターの中には野生生物や自然に対し、深い敬意と忍耐を持って向き合い、対話を重ねながら創作活動をされている方もいる。
しかし、誰もが発信者になれる今の時代では、丁寧な創作活動よりも、一瞬の注目を集める内容の方が評価されやすい面もある。私たちは、本来評価されるべきクリエイターたちの情熱や、作品に込められた思いがより多くの人に届くよう、作品の「向こう側」を発信し、応援していきたいと考えている。
その一つが『クリエイターインタビュー』だ。作品の「向こう側」にある制作プロセスや自然との向き合い方、そして作品に込められた思いや願いを取材し、発信していく。動物絵本作家の高岡昌江さんは、丁寧な取材と生き物への深い敬意から、安易な「かわいい」という言葉だけに頼ることなく、思いを込めた真摯な言葉を一つひとつ紡ぎ出してくれた。
また、元昆虫研究者のイラストレーター、横山拓彦さんは、研究者ならではの鋭い観察眼をもって、見る者を圧倒する細密画を描き、生き物の世界の奥深さや驚きを伝えてくれる。クリエイターたちが示すこうした自然への敬意、創作への情熱、作品に託された思いや願い、そして彼らのまなざしを通して改めて発見する“生き物たちのわくわくするような魅力”を伝えるインタビューを、順次公開していきたい。
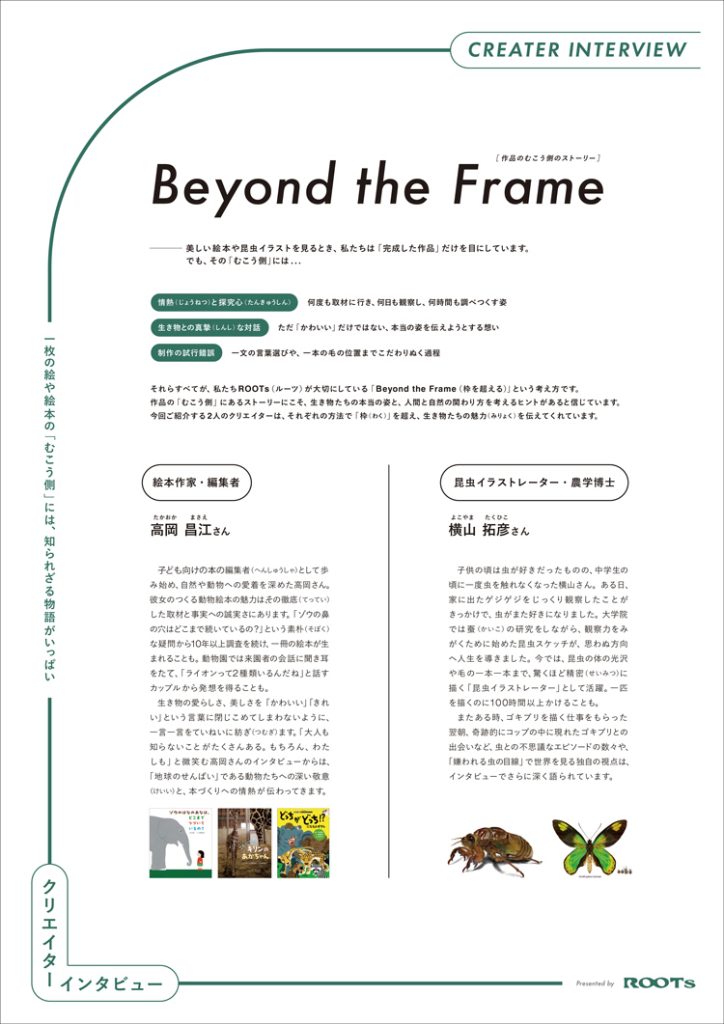
メディアが持つ力は、野生動物にとって「両刃の剣」だ。大切なのは、私たち一人ひとりがメディアの情報にどう向き合うか。一つ一つの映像や写真の裏にある影響を想像し、画面の向こう側にいる「命」を思うこと。そうした意識の変化こそが、「野生生物を守りやすい社会」を築くための、確かな一歩になると信じている。






