
提供:NPO法人環境テクノロジーセンター
「あなたは、科学と技術の違いがお分かりですか?」
高速増殖炉「もんじゅ」(28万キロワット、福井県敦賀市)で1995年12月、冷却材のナトリウムが漏出する事故があった。この事故についてインタビュー取材していたとき、元日本学術会議会長で、日本を代表する科学者の近藤次郎さんから投げかけられたのが、この質問だった。
98歳の近藤次郎さんは2015年3月28日、老衰のため東京都内の病院で亡くなられたが、取材のやりとりには、その人柄がしのばれると同時に、技術の本質、翻って、ものごとの根本から考えることがいかに大切かを示すものだった。エピソードとして紹介したい。
「もんじゅ」は原子炉内で、高速中性子を使って核燃料のウランをプルトニウムという新たな燃料に変換、そのプルトニウムの核分裂でさらにエネルギーを取り出す、という工学の理想を追求する原子炉だ。この二次系冷却管に差し込んだ「温度計」が折損、約640キロのナトリウムが漏出し、建屋内で火災を起こした事故だった。細い棒状の温度計さや管が「共振」を起こしやすい形状になっており、直径約1センチのステンレスの管が秒速40センチで流れるナトリウムによって振動を繰り返したあげく、金属疲労で折れ、その管を通して液体ナトリウムが漏れ出したという、設計ミスが原因だった。
この事故について、近藤さんの所見を尋ねたところ、「ああ、あれは不可抗力ですよ」というあっさりした返答で、思わず「不可抗力ですか?」と尋ねたのだ。すると近藤さんの答えが、冒頭の質問の形で投げられたのだ。
理学部で化学を学んでいたので、私自身も「理学」と「工学」の違いは考えていたつもりだったが、近藤さんの説明が秀逸だった。
「ロケットを飛ばすとしましょう。このような形状で、質量がこのくらいならば、この角度、加速度で打ち上げれば、これに応じた弾道を描いて飛ぶ―これを方程式にして示す、ここまでが理学の仕事ですね。でもあなた、示された原理の通りこしらえて、本当に飛ぶと思いますか。必ず失敗する。そこで、どこがいけないのだろうと、あっちを直し、こっちの設計を変えと、試行錯誤の末に、ようやく本当に飛ぶようにする。これが工学です。だから失敗のない技術開発というものはない、ヒット・アンド・エラーがつきものなのです」
これが「不可抗力」と言い切った背景だった。さらに近藤さんの語りは続く。
「高速増殖炉というのは、少量のウラン燃料だけで極めて長期間、エネルギーを取り出せる、ある意味、理想の原子炉です。ところがリスクもあるし、開発は容易ではない。意欲的に進めてきたフランスも中断し、気がつけば日本はこの技術開発の世界の最前線にいるのです。振り返って、日本には一から作り上げた技術というものがあったでしょうか。欧米が苦労して開発し、それをブラッシュ・アップして優れた製品にする、これはお得意だ。でも、本当に自分の手で創り上げてきたものはない。ということで、いま日本は、この新たな技術の創造に取り組んでいるのです。それでは、日本はこのチャレンジを成し遂げようとするのでしょうか? それとも、1回のナトリウム漏出事故でギブ・アップしてしまうのでしょうか?」

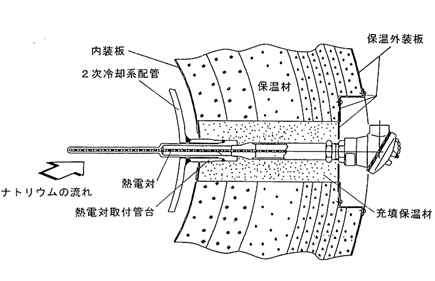
出典.科学技術庁原子力安全局「動力炉・核燃料開発事業団高速増殖原型炉もんじゅのナトリウム漏えい事故の調査状況について」平成8年2月9日
さすがに鈍い私でも、この問いに込められたメッセージ、哲学を感じとらないわけにはいかなかった。そして経歴を見て、改めて近藤さんが積み上げてきた思索の軌跡を実感した。京都大学理学部で数学を専攻、卒業後、東京大学工学部に入り直し、航空工学を専攻しているのだ。理学と工学、まさにそれをつなぐ人生ではないか。
「京都府立一中(洛北高校)では、梅棹忠夫さん(生態学・人類学者、1920-2010)と同級でね、一緒に北山(京都)に入り、昆虫や植物採集をして歩いた登山仲間なのです」
2011年3月の東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故以降、こうした深い思索に基づいた言葉を、科学者、技術者たちから聴く機会が減った。というよりも、多くの人たちのこころに届く科学者のメッセージが、ほとんど発信されていないのではないか。
福島事故の結果、より多くの関心を集めるようになった「高レベル放射性廃棄物」の処理問題、この解決に向けても、近藤さんは大きな足跡を印している。
日本の原子力行政は1963年の発電開始以来、放射性廃棄物処理問題を、先送り、あるいは「見ないふり」をし続けてきた。こうした流れを断ち切り、この問題が多くの人の目につく土俵で取り上げられたのは1994年、「高レベル放射性廃棄物処分懇談会」が原子力委員会に設置されたことがきっかけだった。科学技術庁の廃棄物政策課長だった有本建男さん(現在、政策研究大学院大学教授)が、中央環境審議会長だった近藤次郎さんを説得。近藤さんを座長とする処分懇談会が発足したのだ。
「これは逃げられない問題。国民皆が目に見えるところで議論し、解決への智恵を出さなければなりません」という近藤次郎座長のイニシアチブで、放射性廃棄物問題がようやく市民の目に届くところに現れた。
当時の、環境行政や環境団体関係者からは、「中央環境審議会長という環境問題の元締めが、なぜ原子力に手を染めるのか?」という困惑も聞いたが、「原子力エネルギーと地球環境、これは相反するものではありません。領域を超えた判断、方向性を示すことが、科学者に課せられた務めなのです」という近藤さんの言葉は、現在の科学コミュニケーションが目指す “Interdisciplinary”、狭い領域にとどまらず多角的な評価と価値観を、メッセージとして市民に示す、というコミュニケーションの原点を提示していた。
振り返って、近藤次郎さんが技術創造への挑戦とした高速増殖炉の開発はいま、どうなっているだろうか。
「もんじゅ」はナトリウム漏出事故の後、開発に当たった動力炉・核燃料開発事業団(現・日本原子力研究開発機構)が、事故現場を撮影していたVTR映像の存在を隠すなど、虚偽の発表を繰り返し、組織内部に自殺者まで出して、事故を事件に発展させてしまった。その後も再稼働にこぎ着けてはトラブルを重ね、事故後20年たった現在も、運転再開できていない。福島原発事故に伴う混乱と同じくここにも、「技術」そのものより「人間的課題・Human Aspects」に、問題の所在を見ることができる。
一方、世界はその間、着実にその挑戦を続けてきた。
インドでは2012年から、もんじゅと同じ高速増殖炉原型炉(50万キロワット)を稼働させており、15年4月に来日したインド原子力学会のシブ・アビラシュ・バルドワジ会長は、「もんじゅの開発過程や運転のデータから、われわれも多くを学び、開発に役立ててきた」と語る。
またロシア・ベロヤルスク原発の高速増殖炉BN600(60万キロワット)は、1980年の発電開始から95年までに、計27件のナトリウム漏れ事故を起こしているが、「ロシアの技術者は、事故経験を基に改良を重ねたので、安全性を格段に向上させることができたと胸を張っている」と、ロシアの事情に詳しい技術専門家は話す。同国は昨年、さらに大型の高速炉(88万キロワット)の運転を開始している。
「技術には失敗がつきもの、失敗からいかに学ぶかが大切なのです」
近藤次郎さんの語るこうした論理的思考を、日本の世論、原子力行政、あるいは政策決定者である国会議員はどのくらい身につけてきただろうか。
水泳を趣味とし、大戦後初の国産旅客機「YS-11」の基本設計など、航空工学、応用数学の専門のほか、公害、気候変動、地球環境、原子力エネルギーなど、数多くの領域をつないで活躍してきた。こうした資質は、いつ培われたものなのか。
長女の渡邊凉子さん(67)は、「第2次大戦で研究を中断して兵役に就き、戦後、復学すれば占領下で航空工学科が閉鎖されるなど、研究一直線には進めなかったという経歴から、父が自然に身につけていったものではないか」という。生計のために他の教育機関や統計数理研究所など、さまざまな職場で働いてきたという。聖心女子大で教鞭(きょうべん)を執っていた時期もあり、美智子皇后はそのときの教え子に当たる。
位牌の前には、天皇・皇后両陛下からの弔意が供えられていた。

近藤 次郎(こんどう じろう)氏
滋賀県生まれ、東大名誉教授。1985-1994年、日本学術会議会長。2002年、文化勲章。国立公害研究所長、ブループラネット賞選考委員長、国際科学技術財団理事長、日本原子力産業協会特別顧問などを歴任。
→「空飛ぶ科学者 近藤次郎のHPへようこそ!」
ポートレート写真提供:NPO法人環境テクノロジーセンター

小出重幸(こいで しげゆき)氏のプロフィール
1951年東京生まれ。日本科学技術ジャーナリスト会議会長、政策研究大学院大学客員研究員。元・読売新聞科学部長、元・英インペリアルカレッジ科学コミュニケーション大学院研究員。北海道大学理学部高分子学科卒。76年に読売新聞社入社。社会部、生活情報部、科学部などを経て、2005年6月から編集委員。地球環境、医療、医学、原子力、基礎科学などを担当。主な著作に、『夢は必ずかなう 物語 素顔のビル・ゲイツ』(中央公論新社)『いのちと心』(共著 読売新聞社)、『ドキュメント・もんじゅ事故』(共著 ミオシン出版)、『環境ホルモン 何がどこまでわかったか』(共著 講談社)、『日本の科学者最前線』(共著 中央公論新社)、『ノーベル賞10人の日本人』(同)、『地球と生きる 緑の化学』(同)など。




