16年間のテレビ局アナウンサーを経て、40歳で新たな研究の世界に飛び込んだ桝太一(ます・たいち)さん。2022年4月からは、同志社大学ハリス理化学研究所で専任研究所員(助教)として、研究活動とテレビでの実践を両立させている。10月26日(木)のオンラインイベントを皮切りに11月18日(土)、19日(日)に東京・お台場で開催される科学イベント「サイエンスアゴラ」の推進委員も務める桝さんに、研究者を目指すに至った思いや、現在の活動について伺った。
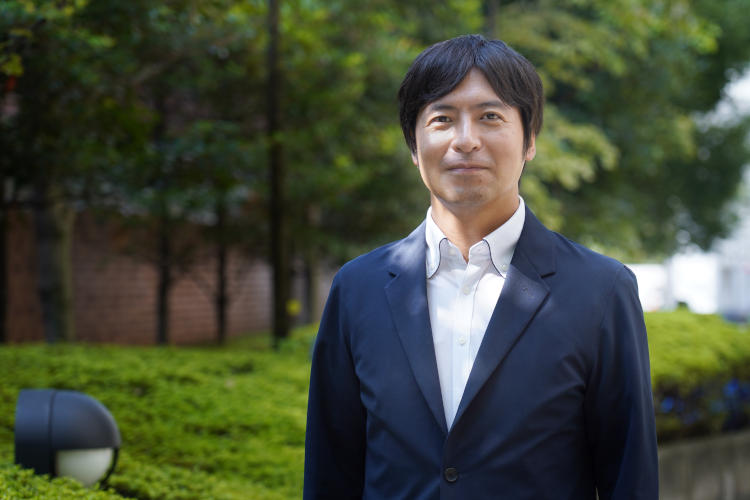
距離の遠さを痛感、ゼロからのスタート
―テレビメディアから研究の世界に飛び込んだきっかけは何ですか。
16年間テレビ制作に携わってきた中、特にテレビメディアとアカデミア(学術研究)の間の“距離の遠さ”をずっと肌身で感じ続けていた、というのが一つのきっかけになっています。

さらに、「東日本大震災」と「コロナ禍(新型コロナウイルス感染症のパンデミック)」という、科学が深く関わる事象が国民全員にとって自分事となった2つの大きな瞬間をキャスターという立場で過ごしたことは、私にとって大きな経験でした。メディアとアカデミアの間がこのままつながっていない状態は、おそらく市民全員にとってマイナスだし、メディアや科学者側にとってもマイナスになるだろうと感じました。
東日本大震災の頃は私自身まだ駆け出しだったので、仕事をしながらもやもやとした思いだけを抱いていました。それから月日が経ちコロナ禍を経験したとき、これはやはり自分に何かできることがあるのではないか、と強く認識しました。ちょうどその頃、私自身がアカデミアと接点やご縁があり、挑戦するチャンスもいただけたので、踏み切る決断をしました。
―研究者になられて1年半ほど経ちますが、驚きや苦労などはありますか。

まずは純粋に、研究者はやっぱりすごいな、と改めて認識させられました。アカデミアで求められる情報の精度や解像度の高さは、メディアで求められるそれとは全く違うというのを実感しています。
それと、研究者が読まないといけない文章量に驚きました。特に私の場合は、修士までの研究とは全く別の分野なので、研究手法も背景も全てゼロからのスタートです。この1年半は、研究の世界に慣れるためにとにかく本や論文を読み、周りの研究をたくさん見る、というのをひたすらやっていた感覚です。
テレビはサイエンスコミュニケーションの最有力手段か
―桝さんは現在、科学情報やリスクの伝達、社会全体の科学意識を高めるなどの役割を持つという「サイエンスコミュニケーション」の研究をされていると聞きます。大学院修士まで研究していた生物分野などは目指さなかったのですか。
全く考えませんでした。16年間全く違う世界にいた人間がぽっと戻れるほど、研究の世界は甘くないと思っています。
その点、科学情報の伝え方や市民との接点を扱うサイエンスコミュニケーション分野なら、自分の16年間のテレビメディアでのキャリアを強みとして利用することで、研究の世界でもできることがあるのではないかと考えました。
―現在の研究テーマはどういった内容ですか。

大きなテーマで言うと、科学にあまり関心のない方々にまで届いて共有できるサイエンスコミュニケーションという発想で、最有力の手段が今のところテレビメディアであるという仮説に基づいて、それを量的にも質的にも解き明かしていく研究になります。
研究を考えるときの前提として、私は「万人に科学は必ずしも必要ではない」というところから入るようにしています。それは、人それぞれ、人生でもっと重要で切実なことがたくさんあると考えるからです。生活のことかもしれないし、恋愛や学業、芸術やスポーツかもしれません。
他でもない私自身がもともと、「周りの人はなんで科学のことを分かってくれないのだろう」という思考でしたが、テレビの仕事で多様な方々や情報に触れたり伝えたりする中で、多くの人にとって科学が一番大事なわけではないし、それが普通だということを素直に理解していきました。
だから、普段から誰もが科学のことを強く意識していなくても良いと思っているんです。ただ、世の中には震災やコロナ禍のように、市民全員が否応なしに科学に基づいた判断を迫られる事態が、ときには起こります。そうした「いざ」というときに、誰もが科学の世界にぱっとつながれるホットラインのようなものを、サイエンスコミュニケーションを通して開通させておくべき、というのが私の考えです。
日常的に科学について信頼できる存在を緩やかに作っておいて、市民側も心のどこかで科学という存在を意識している、というくらいの社会になると良いなと思っています。そして、こうした機能を担う存在として、メディアが多様化した現在もテレビメディアの役割はまだまだ大きいんじゃないかなと、いう考え方なんです。
―テレビにはこだわりがあるんですね。
はい。海外の研究でも言われていることですが、やはり商業放送の持つ汎用的なリーチ力の高さというのは昔からずっと言われていることで、現状、くまなく幅広い人たちまで届けるには未だ既存マスメディアが強いと考えています。自分が現役でテレビにも携わっているからこそ手に入るデータを利用した研究を進めていきたいです。
「アゴラ」の方向性、ゲームショーにも見本市にも
―来週から開催されるサイエンスアゴラの推進委員も務めています。イベントをどのように見ていますか。

サイエンスアゴラで出展されるブースやセッションは、子どもや一般向けのものもあれば、科学へ関心の高い層に思い切り寄せたものもあり、そのグラデーションを感じられるという意味で非常に興味深いと思っています。
私の考えでは、受け手の科学への関心度合いによって伝えるアプローチの仕方はそれぞれ異なり、また伝える担い手も違うべきだと捉えていて、サイエンスコミュニケーションにはそうしたグラデーションがあるべきだと思っています。対象の広さも内容の深さも違うコミュニケーションが、なだらかにつながっていることで、はじめて市民全体に行き渡るだろうという発想なんです。こういう場で、出展者同士が互いにヒントをもらい合うことで、さらに発展していけると思っています。
―今後、どのようなイベントになっていくと良いと考えていますか。
いろいろな可能性があると思います。一つは「東京ゲームショー」の科学版のような存在になること。ゲームショーはゲームファンだけではなく、ビジネスチャンスを探す人たちも集まりますよね。一般客もビジネス客もそれぞれ違う目的で来て、それぞれ得られるものがあるようなイベント設計の仕方があると思うので、参考になるかもしれません。
その他には、「科学を伝える人たち・手法の見本市」という方向もあります。個人的には、イベントを通して多くの方に科学を伝えることと同じくらい、科学を伝える人たち同士の交流の場になることが大事だと思っています。将来どういった役割を担う場になっていくのか、注目して見ています。
ロールモデルの存在を子どもに見せたい
―サイエンスコミュニケーションを広げたり、科学に関わる人を増やしたりしていくために、他に必要となると思うことはありますか。

今、「科学者の顔が見えない」とよく言われます。以前、とある高校で「存命の科学者で思い浮かぶ人の名前を書いてください」とアンケートしたところ、びっくりするほど具体的な名前が挙がりませんでした。もしこれが「スポーツ選手」で聞いたなら、いくらでも出てくると思うんです。
原因には、科学を伝える文化そのものの少なさがあるとみています。例えば、日本人が科学分野で活躍したことを多くの人が知る機会は、現状ではノーベル賞くらいしかないと思うんです。本当は、科学のすごい賞は他にたくさんあるわけですが、そういうことが広く届いていないし評価もされていないと感じます。
科学者についても、憧れの対象となる「ロールモデル」となる人物をもっと見せていけたらと思うことがあります。スポーツなら、大谷翔平さんや八村塁さんの姿を見るだけで、野球やバスケットボールの選手を目指す子どもがたくさん出てきます。科学界にもスターというか、同じように1つの道を極めた先にこんな素敵な人がいるんだ、という現役の人物をどれだけ見せていけるか、ということがポイントだと考えています。
子どもたちがなりたい夢を見つけるときって、その分野自体が面白いかどうかと同じかそれ以上に、「あの人みたいになりたい」という憧れの人に出会えるかどうかが大きいと思うんです。私は中学生の頃からチョウが好きなのですが、もともとのきっかけは、当時同じ学校の生物部で、その人柄や文章力に憧れていた先輩がいて、その人がチョウを好きだったからなんですよ。ちなみに現在その方はNHKで記者をしている方なので、文章力に憧れた私の目は確かだったな、と(笑)。憧れの人の影響で進路が決まるって、実は多いと思っているんです。

―今後の目標などを教えてください。
まずは研究成果を具体的な形にしていくこと、それから自分へプレッシャーをかけるつもりであえて口にしますが、博士号を取得すること。その上で、研究での「理論」とマスメディアでの「実践」の両輪で、自分の考えるサイエンスコミュニケーションの形の社会実装を目指していきたいです。
関連リンク





