1982年、1人の交換留学生がカナダから来日した。それから約40年。環境学の専門家として活躍する彼女は日本の様々な農漁村をめぐり、失われつつある伝統知を糸口にグローバルな課題を解決するための道筋を探っている。地域に暮らす人々の営みから見た日本や科学技術の目指すべき方向性について、上智大学大学院地球環境学研究科教授のあん・まくどなるどさんに聞いた。

何も知らずに日本へ、5年後に再来日
―来日の経緯を教えてください。
父が大学の教員だった関係で幼少期をスウェーデンで過ごし、カナダには中学生で戻りました。グローバルな感覚が自然と身に付き、両親も大人になる前に海外留学をするよう背中を押してくれていたのがきっかけです。
日本を志した理由はシンプルで、姉がオランダに留学したためです。私は別の文化を求めてアジアを考えるようになり、行き先が日本に決まったのは出発のわずか2週間前! 母は「あまりにも文化が違う」と猛反対でした。今思えば母の心配は正しかったですね(笑)。
―苦労があったのですね。
成田空港に着くまで漢字・ひらがな・カタカナがあることや、主に箸を使って食事をすることすら知りませんでした。日本での生活が急に怖くなって、到着日の夜はずっと泣いていたことを覚えています。
―どのようになじんでいったのですか。
大阪のホストファミリーが本当に良い家族で、私の恐怖をよく理解してくれていました。一方で特別扱いをせず、家族の一員として皿洗いなどを任せてくれたのがうれしかったですね。おかげで日本での暮らしに少しずつ慣れることができました。
それでも大陸育ちの私にとって、限られた土地で小さな社会を形作る島国の暮らしは、どうしても窮屈に感じられました。しかしそのことが、資源が有限であることを後の私に教えてくれたのです。
―1年間の交換留学を終え、5年後に再び日本へ。
再来日した1988年はバブル全盛期で、5年間で起きていた変化に驚かされましたね。そのスピードは、私の目には異常なものに映りました。西洋化自体を否定すべきではないですが、それで何が失われるのか、議論が足りないように感じたのです。当時は民俗学が専門だったことも手伝って、日本でフィールドワークを行うことに決めました。

資源と森林の保護は尊敬すべき事例
―資源が有限であることと上手に向き合っている事例はありましたか。
ハタハタ漁が盛んな秋田県八峰町の取り組みは本当に素晴らしいです。町では1983年から92年にかけてハタハタの深刻な不漁が続きました。そこで漁師たちは3年間の禁漁に踏み切ったのです。生活の糧を止める非常に重い決断でした。もちろん反発もあったといいますが、結果的に漁獲量は回復へと向かったそうです。
解禁後は漁網の目を大きくして小さな個体を逃し、資源の保護に努めるとともに、大ぶりな個体を平均的に水揚げできるようになり、付加価値を出すことにもつながりました。現在も若手漁師を中心に産卵場所となる海藻のアカモクを植え、営みを守る努力を続けています。
さらに素晴らしいのは、地域を挙げて森林保護も図ったことです。彼らは山のブナが伐採されたことで水の質・量がともに影響を受け、不漁の一因になったと考えました。以来、ブナの苗木を植林する活動を今も続けています。
極めつけは長期的な目線を持っていること。遺伝子が偏らないよう、わざわざ青森県の白神山地から種を拾ってきているのです。海に生きる人、山に生きる人がそれぞれにプライドを持って使命を全うしていて、尊敬すべき事例だと思います。

―他に日本で発見できたことはありますか。
八峰町の事例のように、陸と海の環境が密接につながっていることです。日本の漁師たちは、伝統的にそのことをよく理解しています。例えば沿岸部の木立が海面に落とす日陰は、魚にとって居心地の良いすみかになります。日本ではこれを魚付林(うおつきりん)といって、明治の頃から漁師たちが積極的に保護してきました。決して特別な技術ではありませんが、こうした知見は科学と対等にあるべきだと思います。

他の国にとってお手本になる活動
―漁師の知見が科学と対等に扱われることにどんな期待がありますか。
禁漁などはグローバルな課題を解決するヒントになると思います。1つの例を挙げましょう。2010年に愛知県で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された「愛知目標」では、生物多様性の保全・回復のために国土の10%にあたる海域を、漁獲などを制限する保護区域に指定する合意が取られました。途上国の低所得者層にとっては死活問題となる数字です。でも、長期的に見たらやらなくてはならない。
では日本の場合はどうかというと、伝統的な禁漁区を合算するだけで10%の1/5、つまり2%の海域をカバーできるという試算がありました。研究者からは猛反対を受けてしまいそうなアプローチですが、漁師の文化は科学と対等な知見なのです。
私の活動では、こうした考えに加えて「対話」「宿題」を重視しています。2012年から実施した石川県能登半島の海女さんたちへの聞き取り調査では、禁漁区をマッピングしてもらうワークショップを重ねました。単にマッピングするだけでなく、ルールや理由、変遷、成果の有無なども落とし込んでもらい、そこに研究者の考えたシナリオを重ねて比較するのです。こうしたやり取りを通して互いの知見を尊重し合い、楽しみながらも当事者意識を持ってもらうべく「一緒に取り組みましょう」と促すことを大切にしています。

―そのような活動もグローバルな課題解決につながりますか。
漁師と研究者が一体となった活動は、他の国にとってお手本になると考えています。実際に私も、科学技術振興機構(JST)のさくらサイエンスプログラム(※)を使ってコロンビアの学生を招き、能登半島などをフィールドに共同研究を行いました。2019年のことです。
ちょうどこの頃、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)から特別報告書が出ました。海女さんたちは自主的にこの報告書を学んでいて、学生たちを驚かせました。日本の漁師が自然の変化に敏感なだけでなく、いかに高い意識を持っているかが感じられたエピソードです。学生たちは、そうした姿勢も母国の漁師たちに伝えてくれていることでしょう。
※さくらサイエンスプログラム:産学官連携により海外の若者を招き、日本の科学技術に触れてもらう交流プログラム

双方向の科学コミュニケーションが重要
―日本が進むべき方向性をどうお考えですか。
西洋型の社会構造は、近年行き詰まりを見せています。グローバル・スタンダードは決して一つではありません。欧米を追うばかりでなく日本ならではのスタンダード―マルチ・スタンダードを目指せば良いのです。
日本の環境は独特で本当に面白い。南北に長い地形は実に様々な環境や生態系を生み出していて、気候変動や生物多様性を考えるのに最適です。加えて研究の質も高く、データもたくさんある。胸を張るべきでしょう。
一方でそれらの研究データは、より多くの使い道があるようにも感じています。具体的には漁師などが持つ優れた伝統知と統合していくことが必要でしょう。日本には長い歴史があります。未来を考えるときに、過去を無視すべきでありません。例えばカナダでは、科学教育に先住民の視点を取り入れるべく「Indigenous Science(先住民の科学)」というカリキュラムができました。こうした事例は参考になるでしょう。
―伝統知と科学的知見を統合するために必要なことは何でしょうか。
科学コミュニケーションが重要になるでしょう。私は『センス・オブ・ワンダー』などを執筆したレイチェル・カーソンが大好きです。彼女は博士号を取るほどの秀才でしたが、論文はほとんど書かずに科学の魅力を伝えることへ人生を捧げました。全ての人に伝えられなくても、1割の人の意識がわずかでも変われば良いのです。
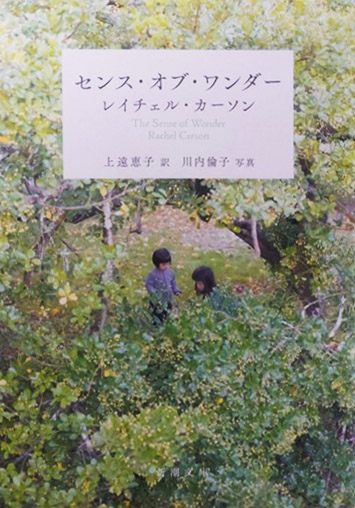
もう1つ重要なのは双方向であること。科学が発展し伝統が失われつつある今、私はステークホルダーが一堂に会する「対話」が必要だと感じています。このとき、科学コミュニケーションの力を借りて互いにレベルアップしていくことが大切なのです。伝統と科学が対等な立場でコミュニケーションを取ることが、やがては統合性のあるアクションへとつながっていくのだと思います。
それはつまり、研究者が上手くアクションを取るためのナビゲーションとしても、科学コミュニケーションが重要な役割を担っているといえるでしょう。
関連リンク
- サイエンスアゴラ2021「海・山・人がつむぐ自然との共生:3.11を越えた未来へ」
- 朝日新聞「『SATO』プロジェクト」(あんさんがナビゲーターなどを務める)
- 上智大学大学院地球環境学研究科「教員紹介」



