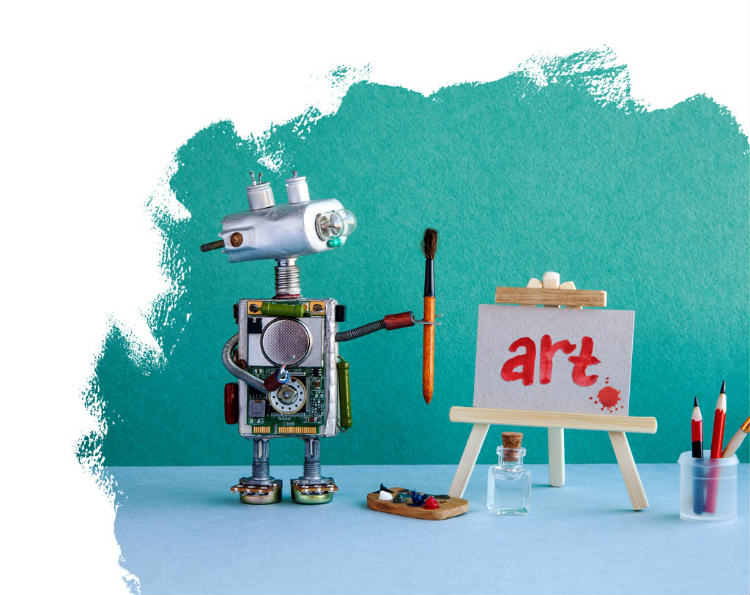
数万年の歴史を持つアート
アートとは、一般的には、絵画、彫刻、音楽、文芸、演劇、舞踏などの創作活動・作品のことだとされている。空間そのものを作品として、観客が体験することで完成するインスタレーションという表現手法もあり、アートを一言で表すのは難しい。
アートの歴史から考えてみると、人類最古の絵画とされるラスコー洞窟(フランス)の壁画が描かれたのは紀元前1万5000年頃。さらにさかのぼって、旧石器時代に作られた土偶など呪術を目的とした原始美術と、表現を目的とした今の美術作品とでは、作られた背景などは違うが、人類が誕生した当時から創作活動は行われてきた。
このようにアートと呼ばれる作品や創作活動は、人間の営みのひとつとして常に身近にあり、時代とともに形を変えて発展してきた。
人の暮らしを豊かにするテクノロジー
では、サイエンス(科学)とはなんだろうか。主に自然科学のことを指す「サイエンス」は、宇宙を含む自然界における「わからないことをわかるようにする」ことだといえる。その中の分野として、生物学や物理学、化学などが存在している。
そして、サイエンスで得られた知見をもとに「できなかったことをできるようにする」のがテクノロジー(技術)だ。新しいテクノロジーが生まれることで、人々の暮らしがもっと便利になったり、問題を解決できたりする。
アートとテクノロジーが出会うと
アートとサイエンスはどちらもアイデアを探究して新しい価値を生み出す知的な精神活動で、その本質はとてもよく似ている。しかし、これまでは別のものとしてそれぞれに発展を遂げてきた。それが今、テクノロジーを通して交わりつつある。
特に、コンピューターテクノロジーは、ビジネスや日常生活を便利にしただけでなく、アートの可能性を広げた。
例えば写実的な精密絵画を描こうとする場合、これまでならばきちんと美術を学び、高い技巧を身につけなければ描くことはできないとされてきた。それがコンピューターグラフィックス(CG)で写真を加工・編集することが可能になり、3D化することもできる。さらにコンピューターの処理速度が向上すると、スマートフォンやタブレットを使って子どもでもCG作品を作れるようになった。
AI(Artificial Intelligence:人工知能)が書いた小説、絵画などのアート作品が誕生し、中には高額で売買されるものもある。コンピューターに人間のような感性を持たせる研究として、アート作品を制作する活動も行われている。
テクノロジーで身近になったアート
アートにおいてデジタル技術を積極的に活用することは、表現の可能性を広げるとともに、人々が作品と触れ合い、体験しやすくするなど、それまで縁遠く感じていたアートを身近な存在にすることにも役立っている。
本誌で紹介する「クローン文化財」は、国宝のような歴史的価値のある作品であっても、すぐ近くで鑑賞できるようにするテクノロジーだ。中には直接触れることができる作品もある。また、スマートフォンアプリ「UDCast」や、音を光や振動にして伝える「共遊楽器」は、誰もが映像作品や音楽を楽しめるようにと作られた。バイオテクノロジーを活用した「バイオアート」は、もともとサイエンスが対象としていた生物や自然界の現象、それらが変化していく様子まで含めてアート作品として表現している。

クローン文化財 (画像提供:東京藝術大学COI拠点)

UDCast

共遊楽器 (画像提供 :金箱淳一)
創作活動をサポートするAIも登場
サイエンスから生まれたテクノロジーによってアートが身近になり、誰もが自分なりの表現を楽しめるようになった。進化し続けるAIは、すでに人間の創作活動をサポートする存在といえるだろう。
いずれは、AI自身が「感性」や「美意識」といった感覚を持つかもしれない。そのような未来を見据えて、私たちは自分の感覚をさらに磨きながら、AIとともに新たな表現の可能性を追求していくのだろう。
アートとサイエンスが交わる世界に触れることは、美しい世界や豊かな未来を考えるきっかけになりそうだ。

AniCastアニキャスト東雲めぐ ©︎Gugenka/AniCast®︎ XVI Inc.
(画像提供:株式会社XVI)

バイオアート (画像提供:清水陽子)





