2011年10月から12年3月にかけて、シンガポール、ヨーロッパ、アメリカの各地を回って「システムバイオロジー」の研究開発と人材育成についての国際動向調査を行いました(詳細はG-tec報告書『システムバイオロジーをめぐる国際動向と今後の研究開発/11CR04』を参照)。「システムバイオロジー」とは、2000年代初頭に台頭し、発展したライフサイエンスの領域で、日本人研究者もこの学問領域の提唱と発展に少なからず寄与してきた経緯があります※1-3。
システムバイオロジーでは、従来の生物学に、数理科学、計算論、情報工学などの発想、手法を積極的に取り込んで、私たち人間を含む生命体が生きていく仕組みを、定量的かつモデル的なアプローチによって解き明かそうとしています。これまでの、実験室の中で生き物や生体試料を相手に、個人がこつこつと観察データを取るような手法とは打って変わり、生体に関するより多くの情報やその映像、画像をコンピューターに取り込んでいくこと、そして、それらを効率的にモデル研究やシミュレーション研究に役立てていくことが求められています。日本では、システムバイオロジーに関係した研究分野について、文部科学省が「生命動態システム科学」という名称で、第四期科学技術基本計画に沿った中で実行計画を進めています。それは、いわば、「生命をめぐるビッグサイエンス」の推進戦略であり、世界第2位の処理速度を誇るスーパーコンピューター「京」などの活用も模索されています。
今回の国際動向調査は、こうした科学的、政策的な流れの中、日本のシステムバイオロジーを担う人材、つまり、生物学の知識とそれ以外のシステムバイオロジーの構成要素分野の知識、経験を併せ持つ人材を「どのように教育、育成していくのがよいのか、特に調べてほしい」という要望を受けて実施されました。調査には、「生命動態システム科学」を推進する拠点センターとして設立された理化学研究所 生命システム研究センターの研究者や、東京大学、岡山大学でシステムバイオロジーについて教育を行う立場の先生たちが同行して下さいました。彼らとの打ち合わせや、その他の国内の有力研究者の助言もいただきながら、述べ1カ月間ほどの時間をかけて、シンガポール、英国、スペイン、スウェーデン、米国での20を超える大学や研究機関、資金配分機関を訪問し、インタビュー調査を実施しました。
インタビューに応じてくださった方々は、研究者だけでなく、センターの運営を専門に行うスタッフ、教育や広報のコーディネイターなど、多岐にわたります。インタビューの受け入れ機関に交渉したり、質問項目を考えたり、JSTのことや調査の目的などを説明する資料を作成したり、インタビューの記録を日本語のレポートにまとめたり、はたまた、飛行機やホテルの手配などと、海外でのインタビュー調査を完遂するのは大変です。しかし、異なる立場の人たちから多角的に意見を伺って、日本のシステムバイオロジー推進に実効性のある研究・教育のプロジェクトの運営手法を提案するのに役立つ情報、ウェブサイトには掲載されていないような情報を入手するためには、避けては通れない重要な調査となります。
今回の調査の主目的の1つであった「人材の育成」について、私たちは英国と米国を中心に、「システムバイオロジー」あるいはそれに準ずる大学院の教育課程を設置している大学の人たちから話を伺いましたが、いずれの大学もさまざまな工夫を凝らして、学生を集め、教育していました。
このコラムでは、米国の例を紹介しましょう。米国では、国立衛生研究所(National Institute of Health、NIH)が、システムバイオロジーを大学教育に導入、普及させて、その人材育成を推進するために、通称「センターグラント」と呼ばれる制度(National Centers for Systems Biology)によって、学生へのシステムバイオロジー教育や一般市民への啓発のために使う予算を配分しています。今回の調査では、このセンターグラントを獲得している大学のうち、東海岸4カ所(ハーバード大学、プリンストン大学、マサチューセッツ工科大学、マウントサイナイ大学)、西海岸3カ所(カリフォルニア大学サンディエゴ校、アーバイン校、サンフランシスコ校)を訪問し、お話を伺いました。どこの大学でも共通していたのが、「生物学とそれ以外の学問領域の知識の両方を体得することが重要」という認識でしたが、その教え方や「1人の学生がどのくらい両方の知識に精通すべきか」という点に関しては、大学によって少しずつ違っていました。
まず、ハーバード大学では、1人の学生が生物学のみならず、システムバイオロジーを取り巻く学問領域すべてを満遍なく理解し、活用できる能力を身に付け、実践できるという「アーティスト」型の人材の育成を前提に研究者教育を進めていました。ハーバード大学は、他の大学に先駆けて、全米で最初にシステムバイオロジーの研究センターを設立し、人材を輩出してきた、いわば、世界におけるシステムバイオロジーのけん引役、リーダー的な存在です。ハーバード大学では、学部課程において生命科学科目は必須となっています。そのような上で、なおかつ学生だけでなく、ポスドクや若手研究者たちも、1人で多様な学問分野を網羅的に理解、駆使できる能力を身につけており、他の大学のセンターで新たに採用されるシステムバイオロジー研究者の多くが、ハーバード大学に在籍した経験を持っていました。そのような経緯から、ハーバード大学は「我こそがシステムバイオロジーの本家」というような自負、誇りを持っているような印象であり、たくさんのスタッフを雇用して分業制で大規模データを獲得し、網羅的に分析するようなやり方の研究(とその推進母体)に対しては、批判的でもありました。
これに対し他の大学は、1人の学生が習得できるのは、生物学プラス1分野程度が現実的と考えていて、いかにそれらをバランスよく学べるか、入学者の選抜段階からいろいろ知恵を絞っていました(ちなみに、ハーバード大学以外で生命科学を必修化しているのはマサチューセッツ工科大学のみでした)。例えば、プリンストン大学では大学院を受験してくる学生のうち、生物学を主専攻とせず、物理学や計算論科学を専攻してきた学生を優先的に合格させ、大学院の教育段階で生物学を教え込む、という方法をとっています。「物理、数学などは若いうちに習得した方がよく、生物学は大学院に入ってから知識を習得するので十分追いつける」と、プリンストン大学の研究者は語っていました。同じような考え方は他の大学にも浸透していて、多くの大学で、生物学を専攻としていなかった学部学生を大学院において積極的に受け入れていました。
それらの大学でよく行われていたのが「大学院生やポスドクによる、異分野融合研究提案のコンペ」です。これは、年に1-2回行われる「リトリート」と呼ばれる合宿形式の行事において、普段は別々の主宰者の研究室に所属する学生やポスドクが1つの場所に集まるのを利用し、その場で共同研究のパートナーを見つけて、今後システムバイオロジーとして進めてみるべき研究課題の提案を一緒に考え、応募書類の形式にまとめあげて審査を受ける、というものです。
優勝者には年間100万円ほどの研究費をきちんと支給するところや、優れたアイディアを提案した人たちに500ドルの賞金(使い道は問わないという)を贈呈するところなど、大学によってその評価、表彰の仕方はさまざまです。しかしながら、このような機会を利用して、若手研究者が自分自身の研究の視野を広げ、異分野からの参画、連携について具体的な事例をもとに考えてもらおう、という意図はどこの大学も同じでした。その中から、NIHの研究助成を勝ち取るような成果が上がっている場合もあるそうです。
ビッグサイエンスとして肥大化、巨大化していくシステムバイオロジーを米国が圧倒的強さで主導している原動力には、このような大学レベルの努力があることが分かりました。まさに、プリンストン大学の研究者が話してくれた、「より広範(Broad)なだけでなく、異なる分野の専門用語をきちんと理解し(Bilingual)、分野間のバランスのとれた(Balanced)人材」、すなわち「3B人材」の育成のために、多くの米国のトップ大学がしのぎを削りながら、模索を続けています。
実はNIHの中でも、こうした人材育成や啓発に特化した資金援助のプログラムはユニークなもので、「その評価を、何を基に、どのように行うべきか」、NIHのスタッフも交えて、今でも議論しながら手法の確立に努めているということを、訪れた大学の人たちが口々に語っていたのは印象的でした。日本がこの分野で国際的にリードしていくにために、このような調査の成果は、今後の投資戦略の決め方や、理化学研究所生命システム研究センターのあり方にも、有益な示唆を与えてくれるでしょう。
今、日本では、かつての大学の教養教育のような「より広範(Broad)な」視野を持つためのトレーニングの機会が失われて久しいように思われます。また、その影響は、各研究領域の第一線の現場を支える人材の能力のみならず、JSTのような——1人の職員がさまざまな研究領域を担当して、研究開発戦略を立案したり、資金配分された領域の設計、運営に携わるような——現場の人材確保やキャリア形成にも及んでいることが予想されます。システムバイオロジーを担う人材育成のあり方は、今後のライフサイエンス研究のさらなるビッグサイエンス化と共鳴して、日本の科学技術力そのものを左右するかもしれないという気持ちで、ステークホルダー1人1人が考えていくべき問題なのではないか、と考えています。
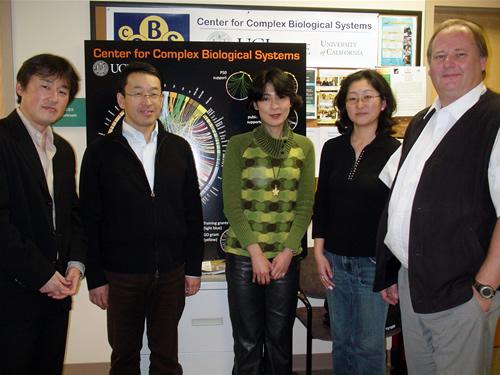
写真左から、米国西海岸調査に同行していただいた大浪修一先生(理化学研究所)、黒田真也先生(東京大学)、中央が筆者。右隣の女性は東京大学出身のKyoko Yokomori先生、現在、カリフォルニア大学の准教授。
参考文献
※1 Systems Biology. pp.1-38, MIT Press, Cambridge, 2001.
※2 Cassman M, Arkin A, Doyle F, Katagiri F, and Lauffenburger D (Eds). Systems Biology: International Research and Development. Springer-Verlag, Dordrecht, 2007.
※3 浅島誠、黒岩常祥、小原雄治編『現代生物科学入門第8巻 システムバイオロジー』(岩波書店、2010年)



